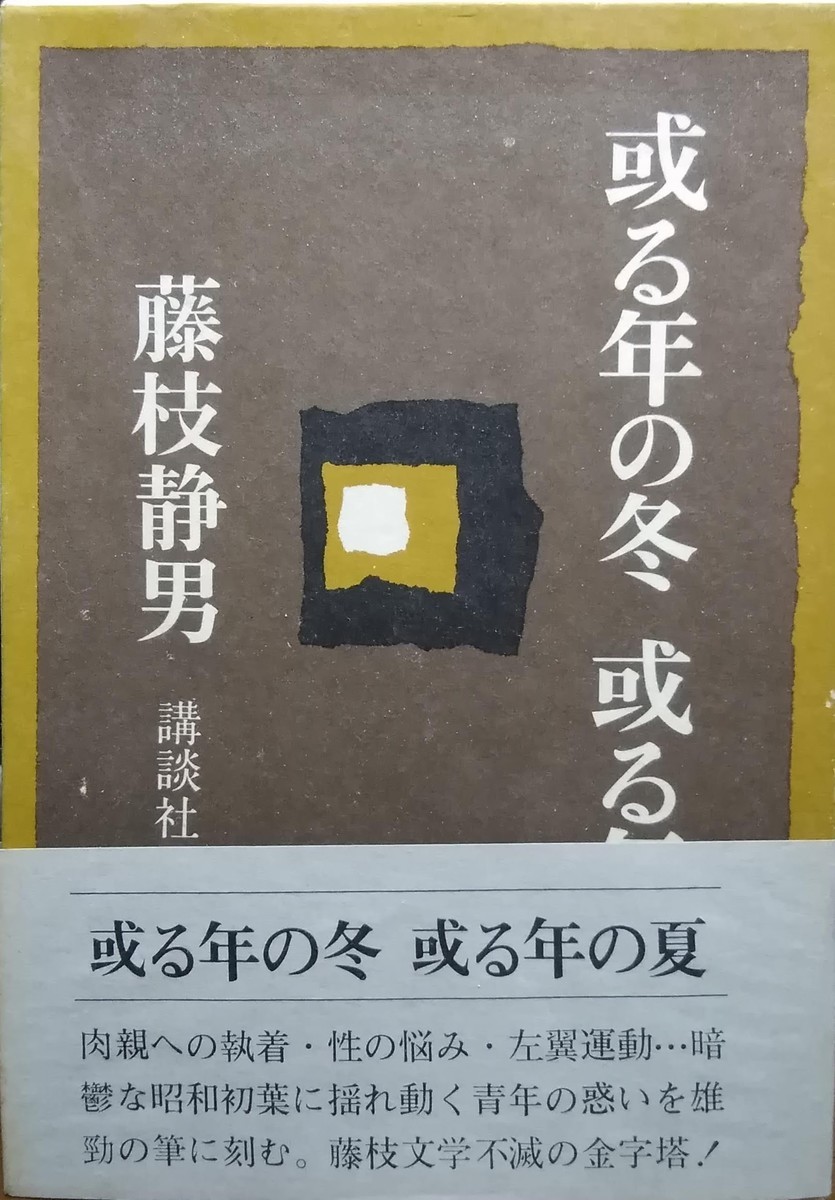ここしばらく百合小説を集中的に読んでいて、ツイッターでもその都度書いていた感想を適宜手を入れてひとまとめにした。アニメや漫画に比べてそういや百合小説ってそんなに読んでないなと思っていた時、百合ラノベ、百合SFが三月くらいにばっと出たのを機に、手持ちのなから百合と呼びうる本を集めたら結構な量になってしまった。積んだままなものもいくつかある。ここでは、性愛でないものまで含めた女性同士の関係を広く包含するものを百合と呼ぶ広めの解釈なので、同性愛を描いたものからバディものや友人関係のもの、一冊のなかの短篇一篇だけが百合というものも並べてある。
以下は読んだ順に並んでいる。とはいえラノベから読み出したので下に行くほどジャンル的に硬くなる傾向がある。
目次
鳩見すた『ひとつ海のパラスアテナ』
陸地すべてが水没し国境線は水平線になった世界を舞台にした海洋SF百合
ラノベ。
電撃小説大賞受賞の百合
ラノベその一。両親を失い少年の格好をして
メッセンジャーの仕事をするアキと「ミズ商売」で生きてきた二つ上のタカが漂流の果てに出会い、仲を深め、そして、という作品。百合だと聞いてたけど三分の一近くまでが主人公の単独サバイバル生活で、浮島に舫った船は消え、生魚を絞って水分補給する孤独でシビアな展開で、ほぼ全てを失いかけた故に同じく操船者を失ったタカとの出会いが奇跡となる。ボーイッシュで操船技術がある少女アキと大人びていて世間知があり家事もできるけど船は動かせないタカの二人の関係が描かれてて、タカから女の子らしい振る舞いを学ぶとともにタカの成長した身体への性的な関心が芽生えていく少年のような心情が同居するアキのキャ
ラクターが特色。そんな二人が一緒に生活して、「寝物語」と称して同じベッドで寝ながらタカからこの世界の仕組みや文化やいろんな話を聞いたり、同性同士の近さにどぎまぎするアキとそれをわかってからかうタカのいちゃつきぶりは、主人公が少年では描けないところだろう。空の青と海の青がどこまでも広がるこの世界で一人でいることの厳しさ辛さを癒やし合う二人の関係が次第に強く堅く結ばれていくんだけど、序盤に対して終盤ちょっと都合が良すぎるのと世界が狭いという点はあるにしろそれは
ジュブナイルらしい優しさか。五年前の
電撃大賞受賞作で、数年前に買ったまま積んでたんだけど、青一色のカバーも鮮やかでなかなか良かった。口絵以外には章扉のカットくらいで、文中イラストがないつくりだったりする。
二月公『声優ラジオのウラオモテ ♯01 夕陽とやすみは隠しきれない? 』
同い年同じクラスの新人声優二人が一緒にラジオ番組をやることになり、ラジオでは仲よさそうに話してるけど裏ではいがみ合ってばかりいて、それでも内心相手の仕事には敬意がありかつ売れてる相手への劣等感なんかもにじみ出す声優百合
ラノベ。
電撃小説大賞受賞の百合
ラノベその二。ギャル×地味のコンビが声優では二人ともアイドル路線で売り出しててという二段階のギャップがある組合わせで、三年目で新人としての期間が終わりそうなのにまだ芽が出ない由美子を視点人物にして、生き残れるかどうかの焦燥感とともに売れてる千佳への複雑な感情を描く。いわゆる「喧嘩ップル」が死ぬほど好きな人が書いた小説、といえばわかりやすい。いがみ合ってても由美子から見る千佳は何度も美少女だと語られてて、そういうラジオでの仲の良さとその裏での現実での仲の悪さとまた本心での相手への感情と、といったコメディと仕事ものを支える複層的な関係がなるほどよくできている。喧嘩をしててもいがみあってても、お互いの声優としての仕事へのリスペクトがあり、それがこの作品の業界ものとしての真摯さに繋がってて読んでて爽やかなのがいいところ。裏と表が雪崩れ込む終盤、そしてここからが本番でもあるという結末。
電撃小説大賞の大賞受賞作で既に一巻のナンバリングがされていて声優ラジオとのコラボやコミカライズまで進んでいるというのはすごいなと思ったけど、読んでみると声優業界ものの面白さもあって、なるほど売れそうor売り出したくなる作品だというのはわかる。ただ、一巻段階だと二人のラジオ自体はあまり面白くないものという位置づけになってしまってて、声優ラジオの面白さを描いてるかというと違う。この手のラジオの序盤はパーソナリティ同士の関係がハマるまではそういうものではあるから、ここは二巻以降の話かな。ラジオパートだと千佳の生真面目さや嘘をつかない性格を知ってる読者と由美子だけがわかる、話の流れで見えてる地雷を自分から踏むことになった千佳が笑える。しかし、ラジオ番組は架空というけどリスナーのラジオネームはなんか聞き覚えがあって実在のをもじってない? 紙の初版カバー裏にSSあるの気づいてない人いそう。
みかみてれん『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』
「
陰キャ」少女が友達欲しさに
高校デビューして「
スクールカースト最上位グループ」に入ったら、そのトップの美人金持ち唯我独尊の完璧人間に惚れられて、一ヶ月間友達と恋人とどっちが良いかの勝負をするなかでお互いの理想の関係性を問い掛けあう百合
ラノベ。同性ゆえ、友達と恋人の間にはどんな違いがあるのかというなかなか核心を突く話になってて、そこから自分たちだけの関係を打ち立てるのは百合の王道感があった。友達に
はぶられた経験故に親友を求めていたれな子と彼女に惚れてしまった真唯とのドタバタコメディで、ぐいぐい押してくる真唯に攻められてどんどん崩されていくれな子の抵抗ぶりがみもので、身体の
接触を官能的に描いてくるし、百合の良さをお前の身体に刻みつけてやるという圧がある。終盤友達を信じることというれな子のクライマックスが描かれる部分で行きがけの駄賃に別人を陥落させちゃうの、お前!という感じですごい笑ってしまったけど、この始末どうつけるつもりなんだ。表面的でない
人間性が見えてきて百合多角関係が交錯する修羅場トップグループ、面白くなってきたね。竹嶋えくがイラストなのもおおと思ったけど、ふりだしにおちる、のむっしゅがコミカライズするというの布陣が強すぎない?と思った。同日買った声優ラジオのウラオモテもこれも同じ姿勢で一緒に風呂入るカラーイラストがあって、なんだこの
シンクロニシティは。ブームか。
みかみてれん『女同士なんてありえないでしょと言い張る女の子を、百日間で徹底的に落とす百合のお話』
女同士なんてありえないでしょと言ってたらクラスメイトのクールな美少女にあなたの百日間を百万円で賭けて本当にあり得ないかどうか試してみない、という誘いに乗った少女との日々を描くソフトポルノ百合
ラノベ。身体の関係から始まるラブストーリーでわりと性描写がある。本篇二百ページ弱のシンプルな話なんだけどきっちりハッピーエンドに持って行く二段階の種明かしもうまく収まってる。まあ実質一冊二人がいちゃついてるだけというやつですね。勝負の形式だったり友達云々だとか話のパーツは同作者の『わたなれ』とも共通してる部分がいくらかあるけど、こっちはかなりストレートに同性愛の話になってて、ビアンバーなんかも出てくるし主人公がいろいろ知って自分の無神経さを痛感する場面もさらっと書かれてる。受動性と主体性のテーマも『わたなれ』に通じるものがある。しかし、これ同人では四巻まで出てて、商業版も続巻決定らしいけど、どう続くんだろう。いちゃつく他にやることがない、と思ったけど一巻も大概そうだったしそれでいいね。
読んだのは三巻まで。昨年末にやっていたアニメを見た後に原作を読んだ。王族の血を引きながら能力を発現させられず、母親の不倫を疑われ政治的抗争の火種になっている
メリダという少女と、彼女を暗殺する命を受けて潜入したクーファが彼女の気高さにふれ、自身の能力を移植する禁忌の秘術で能力を授け、戦闘訓練を施して本当の教師としてともにあることを選ぶ魔法学園ファンタ
ジーラノベ。基本的にこの年上鬼畜教師と
メリダとの年齢差
カップルが主軸だけど、女子校を舞台にしていて、いじめの急先鋒だったネルヴァが
メリダに負けてからはいじめと裏腹の独占欲のようなものをだしてきたり、従妹のエリーの
メリダへの重い好意など、百合要素も強い作品。百合版
ハリーポッターと言われている。アニメから入ると一巻部分はマナまわりが数値化されててゲーム的なパラメータになってるところ以外はあんまり印象が変わらないけど、二巻は三つのイベントが一つになってたり水泳練習がなかったりかなり違う。原作はロゼとのフラグ立ても随所にある。三巻はアニメでのクライマックスにあたり、あるいはここで完結という勢いの総力戦で、老いた魔女の学院長が大活躍し、シェンファ、クリスタらも矜持を見せる盛り上がりが良い。ネルヴァさんは出番薄い。エリーが
メリダガチ勢としての濃度を上げつつ、ミュールも妖しく参戦してくるのも百合ポイントか。学院長の活躍やクーファと
メリダの関係が
擬制的な親と子の関係を示しつつ、血族としての繋がりのモチーフを相対化していく按配。童話にかこつけて着せ替えを楽しんでいる巻でもある。しかし同じシーンを口絵と本文で二度イラスト化してるの笑ってしまった。何が描きたいか明確すぎる。アニメラストは結構オリジナル要素を付け足していてちょっと違う。ジン、マディア、ミュール、
サラシャの関係はさすがに原作のが自然だった。アニメはいきなり仲良くなってたし。「応酬されていく」とか、ところどころ動詞の使い方に違和感があるけど、それも文体か。
『
どろぼうの名人』二部作の
中里十の商業作品としてはいまのところ最後のシリーズだろうか。「恵まれさん」という現金に触れずに他人にものを恵んでもらうことで暮らしている少女とその執事を任じる同級生が
ニュータウンの学校に転校してきたことで語り手と出会うことから始まる百合
ラノベ。資本主義、宗教、同性愛そして言葉のやりとりをめぐる思弁的小説。同性愛者を認める真名と同性愛者でないと言い張る語り手淳子のすれ違い、といえばそうなんだけど、それが「恵まれさん」という独自の設定を介してさまざまな要素が盛り込まれていて、
ジジェクや
チェスタトンが引用されたりなまなかな感想を言いづらい小説で、非常に面白いと同時に謎めいている。恵まれさんをしている絵藤真名の行動として特徴的な、「なんか普通じゃないよな」というような「気持ち悪い言葉を必ず排除する」という行動や、「ふーん、ふーん、ふーん」「へー、へー、へー」という感嘆詞の使い方とかには、
ラノベ的口語文体というより作者が引用している
笙野頼子の影響を思わせる。これ八年前に二巻まで読んでて、続きを買ってなかったので後でと思ったら全巻揃えてからずいぶん経ってしまった。同じ
ガガガ文庫でいうと
樺山三英『
ハムレット・シンド
ローム』を連想させるような挑戦的な一作。
問いと答えをめぐるコミュニケーションの攻防百合
ラノベ二巻。真名との関係ともう一つ、溝口れのあという父の再婚相手をめぐる関係が軸で、男に媚びを売ることが習慣化している「女の敵」は、淳子が上手を取れるほど簡単な人間ではないことがわかってくるのが面白い。「この家でなにが『普通』なのか、私にはわかんないから」というれのあの両親は「貧乏、無学、暴力」で、祖父の遺産で暮らしている淳子の家庭と鋭い対比をなしている。一巻の「どうして空は青いの?」というサブタイトルが、娘、縁、淳子によって問われたように、二巻は「私のどこが好き?」という問いが二度問われる。しかしこの問いかけに対する真名の答えは笑ってしまった。この関係、すごい。淳子の「私の願いはただ、恋人や友達という枠に入らずに、真名のそばにいること」、というのが自分と相手だけの特別な関係、という方向に行くかと思えば煮え切らなさがあるというか、語り落としがありそうというか。愛をめぐる問いがテーマで、れのあの問い方は逆説的で真名の答えは、なんとも言いようがないな。真名が未来を指すなら語り手の淳子は過去を見ている、という語りの枠組みにもかかわるか。思弁的と形容してたら二巻にspeculativeという言葉が出て来た。
「そんなもの誰が買うの?」という副題通り、資本主義と宗教と芸術がサブテーマとして絡んでる。人をだまくらかす恵まれさん、十億以下では売らずにライフスタイルとしても意味をなさない父の芸術は、経済ともかかわりつつ異物でもある関係を取り持つ。エピローグは予感はあったけど、そういうことか、と。あれから22年後という時間をめぐる話。淳子と真名の関係は、肉体関係それ自体よりむしろ手をつなぐことのほうが印象的。「手をつなぐ。と、幸せになる。なにもかもがただこれだけだったらいいのに」 二人で過ごす幸せな時間の描写が、それはもうここにはない、という感触とともにあって、「真名のそばにいることを、否応なく運命づけられていたらよかったのに」というのはどうしようもなくそうではないことと同様。淳子の欲望はしかし、妹というかたちが良いのかどうか。広告としての恵まれさんの期待を抱かせる、というのは誘惑の恥ずかしさと絡んでるか。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』が引用されるし、一巻で
樺山三英の名前を出したらジャン・ジャックの名前が出て来た。
名字が絵藤、なるほど?という謎をさらに差し出す最終巻。
ディスコミュニケーションを繰り返し、言葉をしばしば受け取り損ね、関係を取り結ぶことにも幾度もつかえながら、言葉と、言葉にできないもので結びつく、内井のような「講釈」を拒絶したところで書かれる関係の様相。当時においては幸せとは感じなかった記憶をいま思い出しているなかで幸せだと感じられるのが錯覚だといい、錯覚で良ければあれは幸せの記憶だ、とあるのはさまざまな語り落としが存在するこの小説において書かれていることが、その幸せの記憶だということなんだろうか。高いタイヤを買ったことただ歩いたこと服装のこと、些細な記憶。最後の会話はここで再び会うことの約束で、冒頭の手記はそれが別のかたちで果たされたことを書いた、と受け取っておこう。紙束になった二人。手をつなぐことから指先を触れあわせることへの変化や、副題の問いにいいえ、の意味もよくわかってないけど。作中の描写に対応してか三巻と四巻は表紙イラストで手を繋いでいる。弱さを拒絶する真名、たいしたもんだけどろくでもないというのはこのことだろうか。真名の前では弱さを一切見せなかった縁との関係は何なのか。娘の存在が淳子のある将来を示しているように見えて、そうではないことを明かすのはおおと思ったけど、しかしまた別の謎も出てきたな。執事になったり「恋人」と呼んだり、妹、家族、さまざまな関係と名前のある関係を嫌ってしかし紙束になった、と二人の子が記す。副題がすべて問い掛けになっているように、この小説自体がどこか読者への問いにもなっているよう。百合ではしばしば二人だけの関係性というようなことが言われるけれど、今作ではあえていえば、答えとしての関係ではなく、問いとしての関係が描かれていた、とも。最初から読み返さないと何もわからない奴な気がするな。この、関係を固定化させないかのような描き方は著者が
ユリイカの百合特集に書いた「解放区としての百合」(「
ユリイカ」2014年12月号)での議論がやはりベースにあるんだろうか。
陸道烈夏『こわれたせかいの むこうがわ ~少女たちのディストピア生存術~』
過日カルト宗教から百合で目覚めた人というのが話題になったけれど、つまりそれです。語弊がありますね。宗教的
独裁国家でラジオから聞こえる外の知識を学び大事なもののために外へ出ようという少女二人のバディもの、つまり百合
ラノベ、と言ってしまおう。少女二人とラジオ、
電撃小説大賞同期の『声優ラジオのウラオモテ』とそこが被るとは。しかし読んでてすごく
ライトノベルだ!って思った一作だった。親を失った「子供」が仲間とともにこの壊れた世界の裂け目を見つけ出して生き延びるための術を学ぶという物語の、子供たちよ生き延びろ、というメッセージ。知恵と勇気と友達。世界に差し込む光明は作中ではラジオで、現実ではあるいはネット、あるいはこの小説のような本だ。そしてまた、「こわれたせかい」とはどこなのか?
ディストピアとはどこなのか? 社会、学校、カルト、家などのさまざまな現実の牢獄でもあり、また民主主義国家としての体裁を破壊し違法脱法不法がまかり通るなかで不況と災害が襲いくるいまこのとき我々が生きている現実でもあるように感じるのはあるいは作者は想像していなかったかも知れないけれども。声優ラジオが良い作品なのは間違いないけど、本作の生き延びろ子供たち、という
ライトノベルらしさあふれる点、大賞っぽいのはこっちの気がする。『ひとつ海のパラスアテナ』とも似た、過酷な世界をサバイバルする少女二人、という点が被るのがマイナスだったのかな。
小川一水『ツインスター・サイクロン・ランナウェイ』
元は百合SFアンソロ『アステリズムに花束を』収録短篇を長篇に仕立て直した一作。男女夫婦での宇宙漁という強固な性別役割分業制度を持つ社会で、異なる氏族の女性同士がコンビを組み、固く結ばれていく過程を描いた萌え百合
フェミニズムSF。短篇版と大筋はほぼ同じながら、この惑星での昏魚(ベッシュ)という魚のような存在についての謎や差別的な社会制度、テラと
ダイオードの関係や生い立ちなどなどかなり掘り下げられていて、一長篇としてきっちり膨らませられている。テラと
ダイオードの育った社会それぞれの女性が受ける社会的抑圧の描写を散りばめながら、長身で豊満な体型のテラがその身体ゆえに受けてきたセクハラが嫌だったということの
言語化を促したり、男尊女卑社会で女同士の漁という
同性婚的関係が激しい抵抗に遭いつつ乗り越える
フェミニズムSFの要素も強い。それでいて、
ダイオードのキャラや言動はかなりオタクっぽいというか作中言われるとおり
中二病的でまた思春期らしい性欲も抱えてたり、一見クールに見えて中身はものすごく感情的だったり、かなり萌えキャラって感じの造形がされている。表紙絵にあるとおりの身長差
カップルで、たぶん
ダイオードは自覚的
レズビアンだけど、テラはいろいろ無自覚でその差も肝になってて、むしろ率直に好意を示すのはテラのほうだったりする。同居パートも新しく書き足されているし
ダイオードの実家パートやテラをエロい目で見ていたのがバレるくだりなんかは笑ってしまう。最後の言い合いなんかはいちゃつきぶりが気恥ずかしいくらいのクライマックス。設定から明白な通り
同性婚を思わせる話で、それをドラマにするためにあえて差別性の強い社会を設定した感じもあり、
フェミニズムSFとはいっても手堅いものの新味があるかというとそうでもないとはいえセクハラ被害の
言語化や性別役割分業の批判はまったくもって現在形の問題でもあるし、百合を社会関係から書くなら
フェミニズム的要素は必然的についてくる、ということでもある。基本ラインは短篇版と変わらない爽やかな女子バディもので、台詞回しとかかなりオタクっぽい方に寄せたのかなという感じもあってそこそこ読者を選ぶ気もするけど、宇宙漁の無茶さともども面白い。映像配信司としての仕事で培った知識が絡んでいるあたり、『こわれたせかいの むこうがわ』ともちょっと重なってる。知識と想像力の翼によっていまここから外へと飛ぶ、というモチーフがいろいろ設定の肝になっていて、SFだなあ。
藤野可織『おはなししして子ちゃん』
芥川賞作家の短篇集。ホラー色をベースにいろんなジャンルの定型を崩していくような作風で、怪奇というか奇想というか、年刊SF傑作選にも
採録されたし、たとえば
岸本佐知子編訳短篇集に混じっててもおかしくないような感じと言えば伝わるだろうか。表題作は子供同士のいじめから話が始まるけれど、ホルマリン漬けの猿が怖い、という怪談めいたネタが、お話をせがみつづける猿という奇怪な話になり、解説でも言うとおり勧善懲悪にはならずに妙な方向に展開していく。話がしたい、語りたい、という欲望の話でもある。そもそも本書を読んだのは所収の短篇「
ピエタとトランジ」が長篇化されたと聞いて、まずはこれからと思ったからだ。「
ピエタとトランジ」は高校生で
ピエタというあだ名の少女のクラスに転校してきたトランジは、事件があると即座に解決してしまう名探偵なんだけど、同時にまわりに殺人事件や人の死を招き寄せてしまう体質を持っている。名探偵ものの長期シリーズは主人公のまわりに殺人事件起こりすぎだろ、というこれはこれで定番の冗談をふまえたメタミステリの枠組みなんだけど、相棒の
ピエタはむしろそれを楽しみ、もっともっとみんな全滅させようよ、とそれをそそのかすようなことを言う。個人的に、百合ジャンルに多いと感じるものの一つが自殺や心中もので、この世界を拒否して自殺する少女という形象はしばしば見るし、その表裏一体のものとして「
少女終末旅行」のような少女とそれ以外が破滅した世界という作品も結構あるんだけど、「
ピエタとトランジ」はこの双方が合流したような感触がある。あるいは「ホームパーティはこれから」が描く、女子高生時代の自分たちが一番輝いていたという思い出を大事にしながら、「○○さんの奥さん」という従属物としての社会性に絡め取られていく悪夢と、「
ピエタとトランジ」の社会をぶっ壊してもずっと二人でいようというのは裏表の関係に思える。関係といえば「今日の心霊」での写真を撮った女性だけがそれが生々しくグロい幽霊を写した心霊写真だとわからない、というのも、死をまわりに招き寄せるという意味でトランジと似た性質をもっている。また、本書で百合といえば「
エイプリル・フール」が挙げられる。一日に一回だけ嘘をつかなければ死んでしまう少女エイプリルの人生と、いま彼女と暮らしている女性がいかに彼女を愛しているかを描いていて、現在時ではエイプリルは四十六歳で、語り手も離婚経験を持つ中年女性同士の関係だ。百合漫画とかでも会社員や大人を題材にしたものは結構あるけれど、中年となるとかなり少ない印象なので、貴重な一作だろう。偏った方向から紹介したけど、他にも現代美術ネタとか成長する本のファンタ
ジーとか美をめぐるSFとか、変な話がつまった面白い一冊。
名探偵にして殺人誘発体質を持つトランジと、彼女と出会ってからが人生の頂点だという
ピエタの二人が、女は子を産め結婚しろという抑圧を拒否し、感染する殺人誘発体質で人類を破滅させながらそれでも二人一緒に生き続けることを選ぶ、強烈な百合黙示録。一個上のところで本書最後に再録された短篇版を読んだ時、百合ジャンルの自殺・心中ものやその反転としてのポストアポカリプスものの文脈を感じたことと、同作者の短篇「ホームパー
ティーはこれから」が表裏一体だと指摘したけれど、大筋はその読み通りだと思った。二人でいることが最高に楽しい
ピエタにとって女子高生時代が人生の頂点でこれから先は、と不安がるけれど、「ホームパー
ティーはこれから」が描いたように、女性が結婚し職を辞めるという人生はその輝きをくすませ「○○さんの奥さん」なる主体性を奪われた存在へと陥りかねない。男一人独身というのも一人前と見なされなかったりさまざまな抑圧があるけれども、女性は子を産むことができるという点でその身体は社会からより大きな注目を浴びてしまう。ましてや女二人が子供も産まずに、となるとよりいっそう「非生産的」と見られる可能性は高まる。で、女子二人が最高に楽しく生きる、という時に対決しなければならなくなるものとして本作が据えたのが、人間は子を産み血を繋ぎ社会を再生産していくべきもの――ひとまず「生殖主義」としておく――という考え方だろう。そして完膚なきまでにそれを否定する。存在するだけで殺人を誘発する体質の
ピエタと、長篇では新たに産科医になってたくさんの赤子を送り出し自身も多くの子を産むことが夢の「森ちゃん」が出てくるのは、この対立を構成するためで、殺人誘発体質が感染するという新設定は生殖主義に対する決定的な否定だ。生殖主義を否定するとはどういうことか。それは隣で誰かが殺されててもほとんど無関心になるというそもそもの探偵小説的前提の瓦解と、別にセックスなんてしたくないという男性の出現など、人類社会の常識的認識の崩壊だ。そんななかで
ピエタはこう書く。
それでも、私は幸せだった。楽しかった。起こってしまった殺人の謎を解くのも、起こっている最中の殺人現場に向こう見ずに飛び込むのも、起こるであろう殺人から依頼人を守るのも、どれも好きだった。234-5P
森ちゃんとトランジの関係はまるでイザナギとイザナミのようだけれど、名前の通りイメージのベースは西洋的で、裏表紙には死神の格好をした老婦人となった二人が描かれている。「非生産的」? よかろう我々は死神だ、というわけだ。ピエタは男性と恋愛したり結婚したりもするけれど、妊娠を提案された瞬間それは瓦解する。ピエタとトランジの関係は最後まで性的な関係ではないというのもここでは重要で、アンチヘテロセクシズムというか、異性との恋愛とともに性愛についても第一のものではなくなっている。女二人がともに生きるということの先にあるのは何か、ということに真っ正面から対決した、ある意味百合の極北のような作品ではないかと思ったけど、こういう人類史的なパースペクティヴの百合作品はおそらく既にあるはず。伊藤計劃『ハーモニー』は、どうだったっけ。しかし、女二人で生きることのためにこれほどの代償がいるというのは逆にどれだけ女性に負荷が掛かっているかということでもある。百合ジャンルは女子高生ばかりみたいなことを言われるけれど、学校を出たときに待っているさまざまな負荷を考えると故なきことではない。トランジが終盤でも着ている日本から持ってきたジャージって、女子高生時代のものだろうか。そうでなくともピエタと出会った頃のイメージがあるいはそこにあるんだろう。また、殺人誘発体質に悩むトランジが「死ねよ」なんて言えるのはたぶんピエタだけのはずで、だからこそのラストだ。年老いても人類を破滅させても二人で生きるという女二人を描いたパワフルで爽快な小説で、感染症後の社会を生きるポストアポカリプス百合SFでもある。
宮澤伊織『裏世界ピクニック4』
まあここらに興味のある人はすでに読んでるシリーズだろう、アニメ化も決まっているネット怪談と
ストルガツキー兄弟『ストーカー』との掛け合わせ百合SF第四巻、説明は省く。AP-1で広がる裏世界探検行、
少女終末旅行ぽいところはある。それはともかく、後輩の焼き餅に巻きこまれてからの小桜怯え同衾からの冷たい声の鳥子のくだり、そして温泉あたりの鳥子はだいぶぐいぐいきてて楽しい限り。ホラーとしてもちゃんと怖いので良い。鳥子、冴月から空魚に執着の対象が変わった感がある。「斧は女を美しく見せる」、それほんとにある言葉なんだろうか? 最近斧ガールが流行っているという噂。
森田季節『ウタカイ 異能短歌遊戯』
精神に感応する「歌垣」と呼ばれる能力を発現させ、短歌によって勝敗を決する競技「歌会」の全国大会を戦う高校生を描く百合小説。元は
コミック百合姫掲載だったのがハヤカワの百合SFとして再刊されたものだけれど、SF性は薄く、架空競技ものの一種とみたほうがよい。ただ、架空競技ものにしては試合の流れが粗くて、選抜不参加の先輩と主人公
カップルの当て馬でしかない。その分、表紙の
カップルがいちゃついてるだけとはいえるけど。ハヤカワ版収録の特別篇が本篇と語り手が違うせいか文章も落ち着いててこれは悪くない。本篇主人公の語りが苦手だったかなあ。『アステリズムに花束を』でも短文コミュニケーションの百合SFを書いており、作者は短詩形式にこだわりがある模様。
瑞智士記『展翅少女人形館』
10年ほど前にハヤカワで展開された
ラノベ作家にSFを書かせる企画のうちの一冊。人類が
球体関節人形しか出産できなくなった世界で、人間として生まれた希有な少女達が暮らす
ピレネーの
修道院に、半人形の少女が現われて起こった事件を描くゴシック百合SFファンタ
ジー。SFガジェットも多いけど概ねファンタ
ジー。噛み合い百合の『あまがみ
エメンタール』の作家らしく、閉鎖的な場所での少女達の関係が嗜虐的な淫靡さで描かれるんだけれど、
ボードレール、「独身者の機械」ほかフランス文学の引用やバレエ『
コッペリア』をモチーフにして、文体ともども耽美と残酷さを強調した作風。淫蕩、頽廃、耽美な雰囲気をつくろうとしていて、古い仏文翻訳的な凝った単語を多用した文章は、こんな単語もあるんだとなかなか凝ってるけれど、文章の感覚が現代的すぎてちぐはぐさと冗長さは拭いきれない。また中盤を過ぎるまではわりと平板で、ページがはかどらなかった憾みもある。文章など全体に借り物めいたところがあるんだけれど、作中、人形が多数のなかでは人間こそが異物となるという逆転がまずあり、人間が人形になる変身譚はむしろ人形という人間の偽物こそが本物になるという価値転倒を内蔵しており、あわせてその結末に奉仕するようになってると読めなくもない。これもポストアポカリプス百合の一種だと言いうる一作で、人間が人形を産むのみならず、人間が人形になるという変身に時間を超えた愛が込められている。「母胎より産みだされた
球体関節人形は、ただ存在しているだけで、人類を滅ぼせる。人形とは、人間などより遥かに強靱な生命であるのだ」(396P)。口づけできない二人と、口づけで命をつないだ二人の対比的円環なんかも印象的かな。中盤以降はなかなか楽しめたと思うけど、もう一段二段何か欲しい物足りなさもある。マグダレーナにはリゼットが乗り移っていて後々何かあるんだと思っていたけど別に伏線じゃなかった。この文体を読んで、齋藤磯雄訳『
未來のイヴ』を開いてみたりしてたら、本作にも『
未来のイヴ』が出てきた。この作者の百合ものとしてはまず『あまがみ
エメンタール』から読むのが良いかな、と思う。別名義の『幽霊列車とこんぺい糖』が百合
ラノベとして知られてるけど、未だ読んだことなし。『独身者機械』は読んでないんだけど、概ね男性において描かれてる感がある反生殖の
機械的エロティシズムを、少女側から書いた一作だと言えるかも知れない。でも人形愛系SFは結構ある気がする。「女の子はみんな、子宮(おなか)でお人形を育てているわ。自分が理想とする姿形の、秘密のお人形をね」(271P)。
月村了衛『機龍警察 自爆条項』
人間が乗り組み操縦するパワードスーツ、機甲兵装が普及した時代、その新型特殊装備の龍機兵(ドラグーン)が配備された警視庁特捜部を描くシリーズ第二作。
IRAから分派した
アイルランドのテロ組織の日本での陰謀と、そこに所属していたライザ、そして家族をその組織のテロで失った鈴石緑の現在が東京で交錯する百合SFでもある。第一作は五年ほど前に読んでそのままこれを読んだ。三人の龍機兵の操縦者は元テロリストなどのはぐれもので、特捜部は警察内部からもつまはじきにされているという警察小説としての構図と、
アイルランドをめぐるテロ組織に身を投じた女性主人公の冒険小説とが合流した感触。上下二巻にわたるテロリストの謀略と龍機兵によるアクションが派手に展開され、魅力的なエンターテイメント小説としての読み応えを持ちつつ、ライザと緑の、テロリストとその被害者遺族という憎悪が絡まる関係を超えうるかも知れない一瞬を百合というならば百合だろう。普段ほとんど喋らない冷たい間柄でも、龍機兵の操縦者とその技術主任という関係は命を預け預けられる関係でもあるわけで、男たちの世界になりがちな警察小説にあってやはり同性の関係がクローズアップされるのは自然な道行きだ。ライザと緑の関係は続巻の『狼眼殺手』でも再度取りあげられているとのこと。
アイルランドをめぐる言葉が象徴的にある種のイメージとして用いられるところや、
アイルランド紛争の歴史をあえて説明しないのは気になるけど、そこは参考文献からたどってくれということか。しかし、キリアン・クインというのは
キラークイーンのもじりだろうか。ライザの父が飲んでいるのは
ブッシュミルズ、確か由起谷たちが飲んでたのはコールレーン、最後に
アイリッシュコーヒーのベースとして使われるのが、ダンフィーズという
アイリッシュウイスキー。
柚木麻子『あまからカルテット』
中高一貫の女子校出身の四人の親友たちが、仕事、結婚・恋愛などの三〇前後の人生を過ごすなかで、食べ物にまつわる問題を解決しながら、四人の友情を育み、お互いに頼りあいつつ同時に自己を確立していく百合というか
シスターフッドを描く短篇集。
直木賞候補にも何度かなってる作家だけど、私は『日本の
フェミニズム』に自身の創作と
シスターフッドをめぐるエッセイを書いていたことで知った。これまでの作品も多くは女性同士の友情あるいはすれ違い・嫉妬といった関係を書いているという。友人同士の喧嘩やすれ違い、既婚と未婚の溝、友人への劣等感や憧れ、経済的な格差、姑との関係など、いろんな問題はありつつも協力して、あるいは友人達を心の支えにして一人で、前を向いた先に報われる未来がある明るい作風。解決が簡単だなって感じもあるけど、それも含めて軽快。ただ、働く女性も結婚すれば家事労働を担うのが当然だというような結婚や恋愛をめぐる価値観がずいぶん古い感じで、これは今作がそういう方向に振ったものなのかどうかわからない。作者は同い年なだけに気になる。勝手に来て他人の生活にケチつける姑、家から放り出すべきではって思ったな。浮気疑惑を扱った一篇に「男と女に、純粋な友情なんて」というセリフがあってこれに妙に引っかかってたんだけど、純粋な友情は同性だけというのは裏返せば性愛は異性間だけという
ヘテロセクシズム、つまり同性愛の排除の含意に感じる。深読みだろうか? 本書は2011年の新年を祝う一篇で終わるんだけど、最後の二篇はおそらく震災後の執筆だろう。むろん震災について一切の言及はないんだけど、本書のラストはブラックなオチではなく、未来への祈りなんだろうな、とは思う。しかし辺銀という名字が実在するのは知らなかった。
アニメ化もされた京都の高校での
吹奏楽部を描いたシリーズの第一作。まわりの空気に流されて吹部に入った久美子が、部員達や同中だった麗奈らを目の当たりにするなかで、押し隠していた楽器への愛を自覚し直す青春小説。久美子と麗奈の関係だけではなく、端々に百合的な描写がある。まわりに流されやすい久美子の性格は中学の経験にも要因があり、北宇治の二年生の過去や部員達の流されやすさについて夏紀がいう「空気」の話が
吹奏楽という集団活動ともリンクするけど、全員で演奏する音楽は個々人の努力と上達
からしか生まれない個と全体のテーマがある。だからこそ指揮者の耳はこんがらがった音のなかから個人の音を聞き分ける能力を必須とする。強豪校にも負けないための休日も潰す部活動にはいろいろ問題もあるわけだけど、そこで斎藤葵という脱落者を描きつつ、しかし無償の活動の熱気があるのは魅力ではある。アニメから原作読む時はいくらか不安があるものだけど、これは想像以上に面白かった。アニメで話や人物はだいたい覚えててだからこそかも知れないけれども、単体でも非常に良くできた作品だと思う。手のひらのシワが名もない町の地図に似てた、なんて迷いの表現は印象的だ。アニメと結構違うなと思ったのは大吉山を登るくだりか。アニメ一期八話はとりわけ印象的だったけれども、小説でもデートとか愛とか言うし麗奈が久美子の頬に触れたりはしても、演奏はしないし唇までは触らない。けれど甘い匂いや肌の触れあいに言及する官能的な記述があり、アニメは確かに百合的に描写を盛っているとはいえるけど、原作
からしてそういうところがあるのは確か。久美子視点でもあるのか地の文にはかなり少女の身体へのフェ
ティッシュな目があって、そういうカットも多かった印象があるアニメはなるほど「原作通り」だった。というか少女が感情を激発させるシーンでしばしば同時に身体へ目線が行っていて、作者はそういう感情的な少女の姿に関心がある気がする。久美子が同性の他人の身体に非常に興味があるのはもちろん成長のテーマの一環で、秀一の靴の大きさや髭に関心を持ったりするのはそれだ。とはいえ麗奈が美少女だと繰り返すところぐらいならまだしも、耳をかじったらとか背中をさすって下着に触れたり太ももがどうとか、いやこれは違うなってなる。生々しい感情は生々しい身体から生まれるという巧みなレトリックともいえるけど、あすかと晴香の関係にも不穏さは見え隠れしてる。まあ原作では
高坂麗奈の本格的な登場は200ページあたりからで、ようやくここでメインヒロインかという感じだったし吉川優子もリボンつけてる描写はないし滝昇もメガネの言及は確か、ない。アニメは諸々ドラマチックに盛り上げたり厚みをつけたり、さまざまに変わっている。秀一とのラ
ブコメ感はあるけど、性格悪っと久美子に関心を抱いた麗奈と、その本気の涙が心に刻まれた久美子との二人の関係で閉じられる本作はやはり二人の話。面白かったのは秀一が久美子以外の女子が苦手という情報。これはなかなか味がある。緑の圧のあるキャラも結構面白くてかなり芯のある人物なのがわかる。あと、京都が舞台でほとんどの人物は方言で話しているのがやはり小説最大の強みだ。女子でも普通に「クソ~が」とかかなり率直な言葉づかいをしていてとても良い。久美子の性格の悪さとかも作者がちゃんと底意地が悪そうでそこも信頼できそうって思った。これが大学生の書いた二冊目の小説だというのは驚き。
「僕」という一人称を防波堤にしていた十七歳の女子高生がその「僕」と別れを告げるまでの心理をたどった1990年の
海燕新人文学賞受賞作と、学
園都市、
学生寮のルームメイトとの関係を描いた91年度の
芥川賞受賞作の二中篇を収める、百合要素も強い小説集。「僕は
かぐや姫」は
センター試験出題で話題になった一作。千田裕生は女子校の文芸部員で、自分を「僕」と呼ぶ。十七歳という年齢にこだわり、繊細で傲慢で反抗心にあふれ、美学を重んじ、早熟でそして相応に幼くもある少女の複雑な自意識と、そんな孤独を愛する部員たちが集まる文芸部を描いている。
「女らしくするのが嫌だった。優等生らしくするのが嫌だった。人間らしくするのも嫌だった。どれも自分を間違って塗りつぶす、そう感じたのはいつ頃だったろう」(46P)
「女子校では誰も女性である必要がない。皆、ただ一種類の人間でありさえすればよかった」(49P)
「少年という言葉には爽やかさがあるけれど、少女という言葉には得体の知れないうさんくささがある」(57P)
それだけではないけれど、「僕」にはそうしたジェンダー的抵抗が込められており、また同時に裕生は付き合っていた男を同級生の少女に恋をしていることを理由に別れる。タイトルの「僕」はおそらくはカギ括弧を付されるべきで、自分自身のことを指すだけではなく、かぐや姫のように月へ帰ってしまう自分の物にならない「僕」を指してもいる。十七歳最後の二週間に自らを守ってきたものに痛みとともに別れを告げる過程。文芸部員が普通に煙草吸うし酒飲んでるのが可笑しい。90年代頭は女子校でもそんな感じだったのか、ある程度アウトローの表現なのか。バラード『結晶世界』読んでる百合小説確かこれで二冊目で、もう一冊は『ピエタとトランジ〈完全版〉』。「至高聖所」は筑波をモデルにした学園都市での寮生活を描いたもので、不可思議なルームメイトとの生活を通じて、二人がともに親から捨てられたかのような疎外感を持っていることを浮き彫りにしていく様を描いている。主人公の沙月は美人の姉を親のように思いそして「姉を愛していたから」こそ、姉が音大受験に失敗したあと家族の期待を拒否し家を出て働き、結婚してしまったことに衝撃を受ける。ルームメイト真穂もまた実の親を二人とも亡くしてしまい、義理の父に対して「娘」を演じている。学園都市と鉱物、ギリシャのアバトーンでの夢治療を題材にした真穂の書いた戯曲。ひんやりとした鉱物的世界のなかで、眠りと夢によって「淋しいと言って泣くことを淋しいと感ずる以前に拒絶してしまったそんな淋しさ」を交信したのかも知れない、という一篇。武田綾乃につづいて京都在住作家だ。松村栄子といえば菅浩江さんがイベントのトークで家が隣だったと話していたことを思い出す。今もそうなんだろうか。
このジャンルでは必読書的な『
ナチュラル・ウーマン』の
松浦理英子の第一作品集。葬儀における笑い屋と泣き屋という二人の女性の関係を描く78年の
文學界新人賞の表題作と、女性二人と男たちの夏を描く「乾く夏」、女子寮で肥満の上級生にいじめられる関係が奇妙な展開をたどる「
肥満体恐怖症」の、百合も含んだ奇妙な関係を描いた三作を収める。元版は80年刊行。「葬儀の日」は笑い屋と泣き屋というものに対して社会的に偏見があるという話から同性愛の話にも思えたけれど、笑い屋と泣き屋は川の対岸同士のようなものという問答からはもう一人の自分という分身物語にも読める。事実この二人の発言は括弧に括られない。とはいえ今作の複雑さはそういう単純な構図には還元しえないものがあり、少年と関係を持って
三者関係になったり、首を絞め合う殺し合いの場面のSM的要素など、他の作品にも通底する特有のモチーフがある。「彼女は死んだ。今日は彼女の葬式だ」この十七歳という年齢ともう一人の自分との別れ、というと直前に読んだ「僕は
かぐや姫」ともテーマが重なる、というか、後の発表の
かぐや姫のほうがこれを踏まえてる可能性があるのかも知れない。「乾く夏」、タイトルは深夜
無人の道を歩きながら放尿していく老人がおり、それが朝までには乾いている、ということにちなんだもの。中心になるのは幾子と彩子の二人の女性と、その恋人達の話で、彩子と別れた後
不能になった悠志が幾子と付き合うものの、幾子は鎖陰で性交に失敗する
不能の話でもある。彩子の「最終的な願望は心中」だという不安定さと、幾子はその元彼と触れあうとき「彩子の抱かれた腕に抱かれている。それは妙に興奮させる事実だった」といい、彩子と性交しているような気分になり、彩子になっている気もして「三位一体」を理解する、という奇妙な関係が描かれている。
「幾子は非常に安らかな状態になっていた。この人とずっと一緒にやって行けると思った。それ以外の望みはすべておまけのようなものではないか」(153P)
という彩子についての末尾の一文は、この夏の二人を描いた一篇での重要なものがなんなのかを示している。男を媒介にした間接的な同性愛のような、何か。「肥満体恐怖症」は関係の複雑さよりもシンプルなストーリーテリングが発揮された一作で、肥満を恐れる唯子が、同室の三人の肥満の上級生からいじめられているんだけれど、唯子の元同室から、愚鈍なのか寛大なのか、いや違う、あなたは「奴隷の役をすることに歓びを見出すマゾヒスト」だと言われる。肥満の身体をフェティッシュに描きながら、彼女たちの吐いた煙を吸うことに嫌悪を覚え、強く彼女とその身体を意識しながら、肉に押し潰される快楽を描く一篇。嫌悪と一体の強い関心、これも百合ですね。たぶん。「唯子はひそかに、健康体をノーマル、病体をアブノーマル、肥満体をデブノーマルと呼んで差別していた」という、このひどいダジャレみたいなのに一瞬笑ってしまったけど、デブがノーマル、という意味にも読めるなあとは思った。
災害後、日本は
鎖国し文明も後退、年寄りは死ねなくなり子供は日常生活に手間取るほど身体が弱くなった汚染された社会で、百歳を超える男とその曾孫を描く表題作と、百合短篇「韋駄天どこまでも」、人間が消えた後の動物たちの会話が繰り広げられる戯曲「動物たちのバベル」など、震災、
原発、言語をめぐる五篇を収めた連作集。「献灯使」は独特の感触がある中篇で、
原子力災害後を思わせる汚染や遺伝の変異といったSF要素を持ちながらも、言葉遊びを語りの駆動因にしている部分が強く、翻訳するとこの言語遊戯的側面が伝わりづらくなってしまいそうなのに、よく全米図書賞受賞したなと。英語を学習することが禁止されて、災害を経て動物たちもいなくなったという環境ゆえに、さまざまな言葉が消えたり微妙にズレたものとして現われており、SF的な現実の変容と言語のそれとが絡み合って奇妙な浮遊感がある。子供こそ身体が弱いために、若さは健康を指す言葉ではなくなり、英語が少しでもできれば年を取っている証拠と言われ、ジョギングは「駆け落ち」と呼ばれるようになり、「
勤労感謝の日」は働けない若い人に配慮して「生きているだけでいいよの日」となり、ネットのなくなったことを祝う「御婦裸淫の日」ができたという。こうした言葉への意識は、無名という名の曾孫の、
「トイレ」の「イレ」に「入れ」を聞き取り、出す場所なのに入れるという言葉の矛盾を感じた。でも「トイレ」という単語は英語から来ていたらしいから、「イレ」は「入れ」とは関係ないのかもしれない。(134-5P)
と考えるところや、曜日の火とか木とかになぞらえて、火曜日は「理科の時間にマッチを使う実験があって火傷するかも知れない」、「水曜日は水の日だからプールで溺れるかもしれない」などと想像をめぐらすところも面白い。震災と鎖国とナショナリズムが絡み、役所が民営化され、法律はどこかで日々変わっているらしい、というポストアポカリプスでディストピアなカフカ的社会において遣唐使=献灯使という外へのコミュニケーションの希求はイスマイル・カダレを連想させるところがある。「韋駄天どこまでも」は、中里十のところでも触れた、ユリイカの百合特集の別の論文*1で「突然の百合」と呼ばれていた一篇。夫を亡くした東田一子は趣味を見つけようと通っていた華道の教室で、束田十子という「美しい女性」と知り合う。二人は喫茶店で地震に遭遇し、避難するバスのなかで服がはだけるほど愛撫し合う。体育館の避難所で二人は一緒に暮らし、一子は「幸せ」を感じていたものの、しばらくして十子の姉と男二人と子供が現われ、十子はそのまま一度も振り向かず去って行ってしまう。そして一子は走り続ける。これもまた奇妙な小説で、二人の女性の対のような名前もさることながら、冒頭から言葉遊びで語りが進行していくのが特に奇異。
生け花をしていて、花が妙なモノに化けることもあるが、たとえばそれは草の冠が見えなくなってしまった時である。「化け花」はこわい。
趣味をもたなければどんな魅惑の味も未だ口に入らぬうちに人生を走り抜くための走力を抜き取られて老衰する、と言われて、東田一子は夫の死後、生け花を始めた。(164P 強調原文)
この書き出しの部分は強調がないと意味がよくわからないけれど、「花」マイナス草冠で「化」、「趣味」を分解した「口」「未」「走」「取」が文に散りばめられている。こうした文字の字形を解体して語りに取り入れた技法が多用されている。東田一子と束田十子は、東から一を引いて束に、引いた一を一に足して十にしたのか、画数が同じ名前になっている。だからといって分身だとも思えず、では何だと言われれば答えに苦しむ謎めいた話だけれど、避難の最中の幸福な一瞬を描いた印象的な一篇。「不死の島」は災害後の日本を外から見た状況が描かれていて、郵便が届かず通信ができなくなり、汚染のために飛行機も飛ばなくなり、放射能で人から死ぬ能力が奪われてしまい、民営化された政府の言うことが信じられない、などの状況が素描される。当初はここから長篇にするつもりだったらしく、本書のなかで一番最初に書かれた作。「彼岸」は「想定外のことが起こらない限り、絶対に安全」だという原発に新型爆弾を積んだ戦闘機が墜落する事故によって日本を離れざるをえなくなった人たちが中国に避難していくさなかの一人の議員の心理を描く。この議員は中国を中傷することで不能が回復することを発見し差別中毒になっていた。大きいものを侮辱することで性的に回復する、というマチズモと言葉についての一篇。中国を差別することで票を得た人間が中国に避難せざるを得なくなる皮肉。「動物たちのバベル」は、表題作からは消えていた動物たちが、人間のいなくなった「大洪水」以後の世界で、人の言葉を通じて会話しながらバベルの塔の建設を計画しているという奇妙な戯曲。人間の言葉で動物たちが人間のこと、言葉のことを議論しあっていて、妙に面白い。特に面白かったのは次の下り。
クマ あんたが文明化している証拠は?
イヌ わたしは少年のにおいがする靴を菩提樹の下の草むらに隠している。それを時々出して、においをかいでエクスタシーに浸っている。
クマ 確かに文明的だ。
224P
イヌ 奴隷って何?
リス 危ない職場で働かないと食べていけない境遇に追い込まれた者のこと。人間たちは二十一世紀以降はみんな奴隷だった。(259P)
言語をめぐるオチも面白い。表紙絵のように不思議で不気味でユーモラス。笙野頼子ほどグロテスクではないにしろ連想させるところもある筆致で、震災後約十年を経て災害をめぐる小説が今また奇妙に時事的に読めてしまう。文庫では分からないけど「不死の島」がいちばん早く、表題作が一番最後に書かれている。多和田葉子は『飛魂』が「非婚」の掛け詞で女性同士の師弟関係の話だった気がするし百合の文脈で読めるヤツだったかも知れないけど忘れた。
「現代はめざましい時代だ。電信局に行けば大西洋の向こうの同僚と意思疎通がはかれる。原理? それは知らないよ。ただ五十年前ならそんなことはまったく不可能で、自然界の法則に反していると決めつけられた。でもいまは電信で言葉が送られてきても、ペテンがあるとは思われない」(144P)
こんな19世紀ヴィクトリア朝の英国ロンドンを舞台に、貴婦人マーガレット・プライアが慰問に訪れた監獄で出会った元霊媒の女性との交流を描く、歴史百合ゴシック小説。原書は1990年刊。霊媒のリアリティや三〇手前の「老嬢」レズビアンの生きづらさが肝になる時代設定が巧妙で、急展開の結末もまた百合だ。手記形式を採る本書メインの語り手マーガレットは明白に同性愛者として設定されていて、慕っていた歴史学者の父亡き後、ある女性との失恋の傷も癒えぬなか厳しい母に薬で管理される行き場のなさから監獄への慰問をはじめ、さまざまな女囚の話を聞いていくことになる。その監獄のなかで、一人どこから手に入れたかわからない菫の花を持った女性に一目見て引き込まれる。この交霊会のなかで人を殺した詐欺師と疑われているシライナ・ドーズのもとに、マーガレットは足繁く通うようになる。
ホワイトとジャーヴィスは監獄の有名な〈仲良し〉で、“どんな恋人よりずっとたちの悪い”カップルなのだ、とマニング看守は言った。あちこち勤めたが、どこの監獄にも〈仲良し〉は いたという。きっと淋しいからだろう。非常に扱いづらい女囚が小娘のように恋わずらいにかかったのを実際に見たそうだ。(98P)
本作では監獄と家庭に相似性があるんだけど、上のくだりは何か現代の学校を舞台にした百合作品のようで、じっさい監獄と学校は近代における人間の管理において似た施設なので、百合の意味はそこからも読めるか。おぞましい監獄の様子や女囚の過去など歴史小説的部分もじっくりと展開されていて読み応えがあり、謎めいた女性ドーズとの交流も丹念に描かれてて、それを土台にした終盤の展開は驚きとともにやはりという感じとなるほどなという納得感があり面白い。ただここに来るまでが丁寧すぎてちょっと長すぎるとも感じる。物語展開のうえでこの長さは必要だとはいえ、同時にあの展開だからこそこの長さが徒になるともいえるので難しいところはある。パノプティコンと呼ばれる一望監視システムを備えた実在したミルバンク監獄が花の形にも見えるのはいろいろ示唆的だ。そういう表現が作中にあったか覚えてないけど。家と監獄、日記という形式、核心の話をしないと何も言えないところはあるけれどよくできてる。「慕情」は原文だとなんて書いてあるんだろう。LOVE? 苦い話だけど百合なくしては成立しない直球の百合小説。この作者は次作の『荊の城』が評判良いようで持ってはいるからそれはまたそのうち。以下は私が読んだ本の旧カバー。作中に名前が出てくるクリヴェッリの絵を使っている。

熱心で戦闘的な
キリスト教徒の母親に育てられた少女が、女性同士で愛し合ったがために「自然にそむく欲望」を断罪され、母と教会から去る決断をする半自伝的小説。原書は1985年刊。『こわれたせかい~』、のところでちょっと触れたけど、これは直球そのものの、百合でカルトから脱する話だといえる。そして密着的な関係だった母から自立する娘の物語でもある。「父は格闘技を見るのが好きで、母は格闘するのが好きだった」という書き出しのようにユーモラスに宗教一家で育ったジャネットの奇妙な人生がたどられるのとともに、苦難や人生の岐路に立つ時にはファンタジックな空想的物語が差し挾まれ、もう一つの人生という物語の意味を描く
物語論をも包含している仕掛けがある。
聖母マリアに倣って孤児の子をもらい受けた母の教育によって、主人公は将来に伝道師を考える熱心な教徒となり学校での奔放な振る舞いが異物扱いされるけれども、母は娘を愛し娘も母を愛していた。彼女の「自分は正しいという確信」は「母はいつだって、物事の道理をきちんと説明してくれた」からだ。子供の頃はある程度教義に疑念を持ったりはしても、家族やコミュニティに属している限り、学校が彼女を排除してもジャネットに居場所はあった。しかしジャネットが女性と関係を持ったことが露見すると、母に監禁され悔い改めさせれる。
愛が悪魔のものだなんて、そんなことがあるだろうか? (174P)
この問題について評議会が下した決定は、支部の人々を驚かせた。それは「聖パウロの教えに背いて教会内で女に力を持たせすぎたことが問題」(213P)だというものだったからだ。母を始めここでは昔から女性が強く全てを取り仕切ってきており、この決定はそれまでのあり方をすべてひっくり返すものだった。さらにはこの決定を受けて、母は「男の真似事ばかりしてきたせいで、神の法を軽くみて、男女の道でも同じことをしようとした」と、上の決定に従う演説を行なう。
母はわたしが自分を恥じるとでも思ったのだろうが、そんな気はさらさらなかった。恥じるべきが誰なのかは、はっきりしていた。もし魂の不貞というものがあるのなら、母こそは立派な淫売だった。(214P)
彼女は「女であることの限界」に突き当たり「男性優位社会」に跳ね返されたわけだ。この、レズビアンは男の真似だからダメだという否定のロジックは個人的になかなか意外で興味深く、何故かというと、本書では男性優位の保守的な立場からのものだけれど、同様の、女性を性的に見るのは男だけだという決めつけの言葉をフェミニズム的な美少女表現批判のなかに見たことがあるからだ。異性愛規範を疑わないという点で両者が一致し、だからこそ、論争のなかで宗教保守と一部フェミニストが野合する瞬間が出てくる。性的な美少女イラストのたぐいそれ自体が差別だとは思わないけれども、それを見たり描いたりするのは男性だけなどという主張は、百合コンテンツも含めた美少女表現を担う女性の存在を否定する直球の差別、それも同性愛差別を含んだもの、だと思っている。このロジックは同様に女性的な行為をする男性にも向かうだろう。それはともかく、教会というコミュニティや母といったそれまで疑うことなく過ごしてきた場所とそこから身を引き剥がす苦さは、
人生で何か大事な選択をするたびに、その人の一部はそこにとどまって、選ばれなかったもう一つの人生を生きつづけるのではないか、と。(268P)
と作中語られるように、時折差し挾まれる聖書あるいは聖杯探索や魔法使いの物語など、作中現実と共通したシチュエーションを持つ空想物語は、もう一つの人生というかたちで故郷を捨てた彼女が現実を理解する方法でもあり、人それぞれの現実のあり方を示すものでもある。母もまた娘を伝道師にする夢を失い、「果物はオレンジにかぎる」という口癖は終盤「オレンジだけが果物じゃないってことよ」と変化している。母とジャネットは一つではないし、別の生きる場所もあるし、女性を愛する女性もいて、「オレンジだけが果物じゃない」わけだ。それはまた今ここと別のどこか、という現実と物語の関係ともいえ、歴史的事実のみが真実ではない、という本作の方法そのものでもある。再会した母親に対して、さほど批判的でもないのは、教会に対して毅然と反抗した闘争心や強さは、母譲りでもあったからだろうか。
『見知らぬ乗客』『
太陽がいっぱい』等の映画の原作で知られる著者が1952年に別名義で刊行した百合小説。クリスマスにデパートで働く主人公がある女性に一目惚れして始まる物語で、恋愛関係になるまでも長いけれど当然この関係は時代ゆえ厳しい結末になると思ってたら違ってて驚いた。女性同士の恋愛小説、以上の事前情報なしに読んでたからなおさら。ニューヨークで舞台美術作家を志すテレーズはデパートで働いていたとき、キャロルという女性と運命の出会いを果たす。テレーズはリチャードという男性と付き合っているんだけれど、その時には一切感じなかった狂気に近いような至福を人生で初めて感じたという。彼女はここで初めて「恋」を知り、リチャードがとても良い人だとは思ってもしかし決して愛してはいないことが重荷になりはじめる。クリスマスカードを送って以来親しくなったキャロルもリチャードを評価してるような態度を見せ、関係は入り組んでくる。同時にキャロルは離婚調停において娘の親権をめぐる問題を抱えており、ここでだいたいの道具立てが揃う。物語が進みキャロルとテレーズが関係を深めると、お互いの男性がそれを執拗に否定し攻撃してくるようになる。リチャードがそういう関係は一過性で分別を失っていると非難するのは同性愛非難のお決まりのパターンだ。しかし二人はさまざまなものを失っても二人で生きていくことを選ぶ。同性愛差別が大手を振っていた時代を考えるとほとんど希有なラストだ。2010年版序文でも、「ハッピーエンドを迎える初めての
レズビアン小説」という話があり、「
レズビアンを主人公とする初めてのまじめな小説であり、最後に自殺を遂げたり、絶望におちいったり、すばらしい男性の愛によって救済されたりする物語ではない」のが『キャロル』だと書かれている。二人が関係を深めるまでの一筋縄ではいかない面倒ともいえる過程も時代と環境ゆえのことで、テレーズが「類いまれなる完全な幸福」を味わう後半の旅行に出た二人をめぐるサスペンスもなかなか緊迫感がある。しかし最大の不安定要素はまさに二人の関係そのもので、キャロルがリチャードを評価してみせたりするのもカモフラージュの一環だろうし、愛の告白に至るまでの長さはその現われだろう。若いテレーズの未熟さと成長、そしてキャロルの厳しい選択を描きつつ、「世界じゅうを敵にまわそうとして」もこの関係を選びとるまでの道
のりを描く恋愛小説。これが1952年というのは本当に驚きの先駆性がある。キャロルは普通に車を持ってて、家でも冷蔵庫から冷たい飲み物を出すくだりがあり、日本の50年代の冷蔵庫や自家用車の普及率を調べると二桁パーセントにも達しておらず、隔世の感があるのも面白いところだった。初版の二年後に出たペーパーバックが百万部近く売れたらしく、男性からもファンレターが来たという。
わたしたちのような関係は いたずらに騒がれると同時にひどくおとしめられているわ。でもわたしには、キスの快楽も、男女の営みから得られる快楽も、単なる色合いの違いでしかないように思えるの。たとえばキスを馬鹿にするべきではないし、他人にその価値を決められるものでもない。男たちは子供を作れる行為かどうかで自分たちの快楽を格付けしているのかしらね。まるで子供を作る行為だからこそ快楽が増すのだとでもいわんばかりに。
(中略)
男同士、あるいは女同士のあいだには絶対的な共感が、男女のあいだでは決して起こり得ない感情が持てるのではないかということ。そして世の中にはその共感だけを求める人たちもいれば、男女間のもっと不確実で曖昧なものを望んでいる人たちもいる。(392P)
作中ちょっと面白かったのは、テレーズが「キャロルの飲みかけのコーヒーを手に取り、口紅がついているところから一口飲んだ」というの、最近のでも見る!と思った。七十年前でも変わらないな、と思ったのと、テレーズが持ってきた土産の蝋燭立てを見せての会話が、
「チャーミングね」キャロルはいった。「まるであなたみたい」
「ありがとう。わたしはあなたみたいだと思ったの」(423P)
というところが、キャロルのいう「女同士」の「絶対的な共感」が指す場面かと思った。しかし、同性愛の特性の一つにハイスミスが言う、男女のあいだではありえない「絶対的な共感」があるとするなら、百合の真髄は双子百合ということになるのではないか。でもこれをさらに進めるとつまり自己愛こそが、という話になるけど、鏡写しの自分あるいは自分の分身との百合ってのもそういやあったような気がする……
政治家夫人クラリッサ・ダロウェイからはじまり、さまざまな人物の意識を数珠のようにつないでいきながら、彼女がパーティを開く
第一次大戦後のある日のロンドンを描く、1925年発表の長篇小説。若きクラリッサが同性とのキスを人生最高の瞬間と呼んでいるので百合ですね。ウルフというと意識の流れという手法で有名で、実験的な小説と思われるかも知れないけれども、今作については確かにある人の語りがいつの間にか別人のものに移っていくんだけど、誰が語り手なのかはまあわかるし、何が起きてるかわからないような難解さはなく、結構読みやすい印象なのは訳のおかげだろうか。今や保守党の政治家の夫人となったクラリッサが、花を買いに出かけるなか、夫との関係や結婚を考えたもう一人のピーターのことを考えたり、インドから帰ってきたピーターがクラリッサに出会ったり、戦争で精神を病んだ夫を持つ妻が二人で公園や医者のもとを訪れたり、娘のエリザベスと、彼女が懐いている貧乏だけど歴史については自信があるキルマン先生のクラリッサへの劣等感、夫リチャードのクラリッサへの愛、そうしたさまざまな人物の考えが相互に入れかわりそれぞれの関係の立体感を立ち上がらせながら、戦後のロンドン社会の空気を描き出している。自殺する元軍人がクラリッサの分身だと作者が言うように、幸福と同時に終わりの不穏さが通底していて、クラリッサは「こんなことがあったあとに、死など到底信じられない――これがいずれ終わるなんて。わたしがこのすべてをいかに愛しているか、世界中の誰も知らない。この一瞬一瞬を……」(214P)といい、ラストでもピーターがクラリッサに恐怖と恍惚を感じている。クラリッサはパーティを開くことについて
わたしはただ生きたいだけ。
「だからパーティを開くの」と、クラリッサは生に向かって語りかけた。(212P)
と語っている。生の一瞬を愛する、というのはまさに今作の仕掛けでもある。また医師ブラッドショーの夫人は、かつての自由に対し「それがいまは夫の顔色をうかがい、その望むところを即座に読み取って従おうとする。夫の目が支配を求め、力を求め、油膜を張ったように光るとき、夫人は身を縮め、硬直し、すくみ上がり、刈り込まれ、後ずさりし、おずおずと夫を見る」(177P)と、夫人という立場の屈従を描いてもいて、「夫人」というタイトルの含意がここにあるようにも見える。また最初に書いたように、クラリッサにとっての人生最高の瞬間は結婚する前のサリーという女性との出来事にある。性や人生のことや社会改革のことを語り合ったとサリーとの思い出を語り、ウィリアム・モリスやシェリーについて語り、
サリーに対するわたしの気持ちは、いま振り返っても不思議だ。純粋、誠実。男に向ける気持ちとは違う。欲や得はまるでなく、女二人の間に――それも成人したばかりの女どうしにだけ――存在する感情だったと思う。(64P)
そして、花を挿してある石壺のわきを通ったとき、私の人生で最高の夢の瞬間があった。サリーが立ち止まり、花を一本取ってから、わたしの唇にキスをした。世界が逆立ちし、周りが消え失せて、わたしとサリーの二人だけがいた。(66P)
クラリッサのサリーへのこの愛はリチャードのものとすれ違っているように見える。このパーティに偶然サリーが訪れ、驚きの再会を果たすときのクラリッサの喜びようが描かれている。古典新訳文庫の解説が言うように、生と死、同性愛と異性愛、結婚と独身、政治家夫人と貧乏人、宗主国と植民地などのさまざまな対立を相互に絡ませながら、それぞれの人物がロンドンのある一日において無関係なようで微妙に絡み合う場になっている。リチャード、ピーター、クラリッサの関係とともに、エリザベス、キルマン、クラリッサの関係もなかなかに不穏なものがある。過去サリーとの間には同性愛的感情とともに「社会改革」への熱意があって、クラリッサの現時点での保守党政治家の夫人というしがらみのある地位にあることへの鬱屈があるようにも見え、だからこそセプティマスの医療からの脱出のような外への志向がわだかまっているのかも知れない。上のほうで藤野可織の短篇「ホームパーティはこれから」に触れたけど、ほぼ同じ話なのかも知れない。しかし百合というなら三大レズビアン小説といわれたうちのひとつ、『オーランドー』を読めばいいのになぜかこっちを読んでいた。
セアラ・オーン・ジュエット『とんがりモミの木の郷 他五篇』
ウルフとともに
『レズビアン短編小説集』に収録されていた作家で印象的だったジュエットが
岩波文庫で初の単独訳書が出たのを見てつい買ってしまっていたもの。1849年生まれの作家による作品集で、老若問わず男性に依存しない女性同士の親密な関係が、地方の自然描写とともに描かれる。メイドの令嬢への愛を描いて感動的な「マーサの大事な人」は120年前の主従百合の古典的傑作。「マーサの大事な人」がもちろんだけれど、本書に収められた作品はいずれも男女間のロマンスや結婚生活の描写が避けられていて、男性も出ては来るんだけれど、女性同士の関係を描くことに力点が置かれており、実質的に百合作品集で、しかも高齢の老女たちの出番がとても多いという特色がある。それもそのはずジュエット自身が生涯結婚せず、アニー・フィールズという女性と数十年にわたるボストンマリッジという女性同士での生活を送った、あるいは
レズビアンだったのではないかと思われる人物で、
シスターフッドあるいは
フェミニズム文学の観点から読めるんじゃないかと思われる。
ヘンリー・ジェイムズや
キプリングといった作家から絶賛された表題作をはじめ、
アメリカ文学史においては地方色・ローカルカラー文学としてしばしば言及される作家らしい。表題作「とんがりモミの木の郷」は、ある女性が執筆の仕事のために
メイン州東岸の海辺の町ダネット・ランディングに滞在した六月から九月頃の夏の数か月を舞台にする。滞在先として選ばれた家の主ミセス・トッドは薬草に通じており近隣の住人に処方をして生活をしている。そのミセス・トッドをはじめ、「わたし」は海辺の町とその周辺のさまざまな場所や人と出会い、話を聞き、静かな町に堆積した小さな物語を知っていく。リトルペイジ船長の語る、氷の果ての誰もいない町という
怪奇小説風挿話や、孤島に暮らした
ジョアンナ・トッドという女性の物語も印象的だ。家主のいとこでもある
ジョアンナは、婚約者に裏切られ、傷心から孤島にひきこもり死ぬまで一人でそこに暮らしたという人物で、ここに結婚への否定性を見ることはたやすい。ミセス・トッドの母親は離れた島で息子と暮らしているんだけれど、二人とも現在単身者で、これは主人公もそうだろう。そして終盤に出てくる妻を亡くした孤独に苛まれている男性含め、作中に出てくる人物は多くが単身の高齢者だ。ミセス・トッドは六〇代でその母は八〇代。そして女性は必ずしもそうではないのに、妻を亡くした男はそのことに意気消沈している。女性の自立、強さが印象的だ。
我々は一人一人が隠者であり、一時間あるいは一日だけの隠遁者である。歴史のどの時代に属する隠者であれ、理解し合える仲間なのだ。(116P)
と、語り手は考える。本書に通底するものは孤独と自然ではないかと思えるけれども、孤独ゆえに親しい友を求め、日々の会話が始まる。そこに土地の人々とその物語が生まれる素地がある。孤独と自然といえば『レズビアン短編小説集』にも収録されていた「シラサギ」は、六月、九歳の少女を主人公として、ハンサムな男性とのロマンスを拒否し、自然を守る物語だ。外からやってきた男性はシルヴィアに一時の夢を与えるけれども、彼はシラサギを撃って剥製にしようとしており、シルヴィアはシラサギの居場所を教えることをやめる。鳥が好きなのになぜ撃ち殺すのか、とシルヴィアは不思議に思うけれども、本篇での狩猟と剥製は性行為や結婚の寓意だろう。彼女が海を見たことがなく、海を夢見ているのは海辺の町の表題作とちょっと関係あるのかな。「ミス・テンピーの通夜」は、故人の一番古くからの友人二人がともに通夜を過ごす四月の一夜を描いた一篇。一人は未亡人の姉の子供を育てており、貧しさと苦労の人生で、片方は農場主と結婚して裕福な生活をしていて、貧富の差のある二人が、ともに故人を思いながら旧交を温める。「ベッツィーの失踪」は救貧院で暮らす三人の老女のうちの一人、ベッツィーが昔勤めていた屋敷の主人の孫娘から百ドルという臨時収入を得たことで、一人内緒でフィラデルフィアの博覧会に行ってくるという小さな冒険譚。ほとんど外へ行ったことがないベッツィーの見るもの全てが新鮮な旅行と、不意の失踪に大騒ぎになって彼女が池に沈んでいるのではないかと思い悩む二人を描いており、三人の老女の仲が一つの軸になっている。これは五月の物語。「シンシーおばさん」は珍しく冬が舞台で、元日の朝、一人で住んでいるおばの元に姪たちがサプライズの訪問をして喜ばせるという暖かい話。「マーサの大事な人」は『レズビアン短編小説集』の時に感想を書いたけど、再読してもやはりとても良い。ミス・パインの邸宅に勤める不出来で何も学べないと思われてたメイドのマーサは、丁寧に仕事を教えてくれた一時滞在者のヘレナに対して深い敬愛を抱き、四〇年を経た再会を果たす。マーサとヘレナが過ごしたのは六月の数週間だけで、ヘレナの結婚式にも参加できないまま、四〇年と言う時を離れて過ごすけれども、その間マーサはヘレナのことを毎日のように考え、外国暮らしをする彼女の所在を地図に記し、彼女への愛を生きることでまるで聖者のごとき人物へとなっていった。
大切に思い、尽くしてきた友が遠くに去ってしまうと、人生の喜びも消えてしまうものである。しかし、愛が本物であったなら、完璧な友という理想の存在に身を捧げたいという、より次元の高い喜びがすぐに生まれる。平凡な幸福が、より高いレベルのものになるのだ。(313P)
この愛が報われるラストにかけての場面はやはり感動的。それでいて、ヘレナの結婚は女性同士の関係を阻害するものになっていて、結婚生活は「喜びも悲しみ」もあるとは書かれているけれど、最後に喪服を着ているということは単身になって初めてマーサと再会できたと読んでいいのだろうか。主人のハリエット・パインにしろ、マーサやヘレナにしろ、独身、未亡人といった単身者の女性たち、という人物配置はやはりレズビアニズムによるものに思える。マーサもヘレナからの手紙の名前にキスする描写があったり、時代ゆえか性的な描写や要素を避けてはいるけど、やはりそうかなと。作品集として面白いのは、表題作が一時滞在のあと別れを迎え、最後の一篇が四〇年ぶりの再会で終わるところ。多くの作品は四月から夏にかけての緑の季節を舞台にしてて「シンシーおばさん」での冬の年明けを経て、マーサは四〇年を経た同じ初夏に再会する構成なのは企まれた編集だろうか? 近くても遠くても待ち人来たる嬉しさ、そして未婚や寡婦あるいは救貧院の、社会の周縁と思われた女性達を共感的に描いている。地方のさらに周縁の存在への共感的視点。解説では『レズビアン短編小説集』に言及しておらず、レズビアンという語を避けたような書き方だけれど、そういう視点からいま読まれる余地があると思うし、じっさい本作品集はジュエット作品でも女性メインの短篇を集めた印象なので、そういう編集意図があるのは確実だと思うけれど、ちょっと不可解。ジュエットについては亀山照夫「セアラ・オーン・ジュウェットの世界 牧歌と自然のイメージ」という論文がネットで読め、未訳が多いのでいろいろ情報が得られる。「老婆を書かせては天下一品」と言われてるのが面白い。ジュエットの特徴として指摘される「幼児的性格」は、過去志向へと裏返り「古風な世界」の擁護としてこれ以上ない特異性を生んだ、と論じられていて、それはそうだと思われるけれども、ここで恋愛体験のなさがその一環として言及されるのはどうかな。「マーサの大事な人」の女性たちは家系として重要でない娘とメイドだったゆえに未婚のまま放っておかれている印象だけれど、そうした周縁的存在だからこそ未婚のままでいることができると裏返して読んだほうが面白い。地方にこもる保守性を、地方の周縁の女性からの批評性として読み換えるというか。フェミニズムや女性の観点というのがないな、と思ったらこの論文は70年代のものだった。
1849年の連載途中で作者の逮捕によって未完に終わった長篇小説。女性の一人称で少女自身の人生をたどるなかに、孤児となったあと引き取られた
公爵家の令嬢との熱烈な愛情表現がある170年前の百合小説。全集の端本を持ってて作品の存在は知っていたんだけど、百合小説のリストか何かで見るまではこういう作品だとは思っていなかったので驚いた。
ドストエフスキーの女性主人公の長篇ということでも非常に興味深い一作だ。全集ならどれでも入ってると思うけど、私が読んだのは新潮社版の1979年刊、第二巻収録の
水野忠夫訳のもの。上下二段組二百ページ弱で、これだけで既に普通の長篇一冊分くらいの長さはある。最終的には数字の通し番号で七章構成になっているんだけれど、解説によると当初は「
幼年時代」「新生活」「秘密」の三部構成になっていたようで、実際に内容面では三部構成といっていい。音
楽家の才能があったのに酒や頑ななプライドで破滅したエフィーモフの話から始まり、夫に先立たれた実母がエフィーモフと再婚したのち、物心ついてからの生活を描く貧困の幼少期と、相次いで両親が亡くなり父の才能を知っていたH公爵に引き取られたその家での生活と令嬢との関係、モスクワに発った
公爵家と別れその親族の家で過ごした八年間と、住む場所がパートごとに変わっていく。第一部の幼少期では、才能があるのに身を持ち崩し、金目当てに再婚した妻に対して自分が金を持ち出して酒に溺れているのに、妻がいるから自分は音
楽家として活躍できないと触れ回るクズと化したエフィーモフの底辺生活と、その父を愛する娘で主人公のネートチカ(本名はアンナで、ネートチカは母親が考えた愛称)の生活が描かれる。娘を使って家の金をかすめとろうとするエフィーモフのリアルなクズさがなかなかつらい序盤だけど、ネートチカは母に怒られる同士ということでかなり最低な振る舞いに及んでいる父に同情しており、あるいは彼に「母性愛」を抱いていたという。あるいはこれは音楽という芸術が本作の後半のテーマになる伏線と思われる。第二部は、父を知っていた公爵の家に引き取られてからの十歳前後の頃を描いていて、孤児となった傷心のネートチカが少しずつ家に馴染んでいくさまと、そこに現われた同年代の少女カーチャとの仲を深めていく過程が描かれる。目が覚めて初めて見た彼女の美貌に
歓喜に包まれたネートチカは「わたしはカーチャに恋をしてしまったのです」というほど「熱烈な恋」に襲われる。以下、初対面の描写。
ふたたび目を開いたとき、目に入ったのは、屈みこむようにしてこちらをうかがっていた、わたしと同じくらいの年頃の少女の顔でしたが、そのほうに手を差し伸べたのが、わたしが最初にした動作でした。この少女をひと目見るなり、わたしの心は、何か甘美な予感にも似た幸福ですっかり充たされてしまいました。ここで、もっとも理想に近い魅惑にあふれた顔、驚嘆すべき美しさに光り輝くばかりの顔、その前に立つと誰でも、思わず快い困惑を覚えながら歓喜に身震いし、そしてなにかに突き刺されたようになり、それがこの世に存在することで、自分がそれに出会えたことで、それが自分のそばを通り過ぎていったということで感謝せずにはいられなくなるような美貌のひとつを想像してみてください。それが、モスクワから帰ってきたばかりの公爵令嬢カーチャなのでした。(319P)
ネートチカはこの感情に振り回され、突然キスをしてしまったりする。しかし優秀さを見せたネートチカにプライドを煽られたカーチャが優位をとろうとしたり、不幸な境遇を根掘り葉掘り聞き出そうとしたカーチャが家庭教師に怒られたり、仲が良いとは言いがたい関係だったけれども、いろいろあって、カーチャもまたじつはネートチカを好きだった、とお互いがベッドで気持ちを告白し合ってからはお互いに百回もキスをしあいながら語り合ったという一夜の描写がものすごくてびっくりする。あなたが寝ている私にキスをしたのを知っている、とカーチャが言い、私のハンカチをどうしたの?と訊いてきて、ネートチカがハンカチを持ち出して匂いを嗅いでいることがバレていた様子が描かれるところとか、どうしてあの時はあんな風だったのかという話になって、好きになりたいのに憎くてたまらなかった、「わかったの、あたしがいなければあんたは生きてゆけないということが、それで、あのいまわしい女の子を苦しめてやろう、と考えたのよ!」とカーチャがその天邪鬼な心情を告白してくるところとか、二人でお互いのすべてを話し合い、これからの二十年間の生活設計をして、お互いが命令と服従の遊びをして見せかけの喧嘩と仲直りをするんだ、という幸福を語るところはドストエフスキーの熱のこもったあの筆致で少女同士の絆を描いていて圧倒される。そしてこの時代なのに、というかこの時代だからこそなのか、あまりホモフォビックな雰囲気がない。表現の激しい強い友情ぐらいに思っていたんだろうか。とはいえ、孤児と親しくなることに「嫉妬」した母親から距離を置くことを命じられたり、幸福な時期は長く続かず、公爵の幼子がモスクワで危篤状態になった、ということでカーチャもともに旅立ってしまい、第三部は公爵夫人の長女夫妻のもとで過ごすことになる。この長女アレクサンドラは、夫人から煙たがられていて、むしろ継父の公爵がよくカーチャを連れて会いに来ていたという。カーチャはこの義理の姉を「熱愛」していたとも書かれている。そこで暮らすことになり、ネートチカはこの夫婦の間にある秘密を知ることになる、というのが第三部で、歌の才能を見出されるのもここだ。母親代わりとなったアレクサンドラとの関係もあるいは百合と言いうるかも知れない。母親のように友達のように親しくなり、あるいは十二歳を過ぎて少女の頃を過ぎたことで、以前のような距離ではなくなったり、成長するにつれて関係はまた変化していく。興味深いのは、夫婦の秘密を通じて巻き起こった騒動のなかで、夫が二度ネートチカをめぐる「嫉妬」を口にすることだ。一度目は妻に対して私とネートチカの関係を嫉妬している、と決めつけ、二度目は自分自身が妻とネートチカの親密さに「嫉妬」していたと告白する。若い少女への恐れ、でもあるだろう。まあそれは良いとして、秘密の手紙をめぐる謎についての騒動もまだありそうなあたりで未完となる。この孤児の少女の成長が、音楽という芸術やカーチャやアレクサンドラなど女同士の絆とともに描かれる可能性もあったように思える。ドストエフスキーの女性主人公の長篇が完結していたらとても興味深いものになったのではないかと惜しい気分だ。これが近代小説において最古の百合小説、とどこかで見たけど、そうなんだろうか? ドストエフスキーの百合だ、といって再刊すればそこそこ話題になりそうな気はするんだけど、やはり未完なところがネックか。
沢部仁美『百合子、ダスヴィダーニャ 湯浅芳子の青春』
番外篇。1896年生まれの
ロシア文学者
湯浅芳子への取材を元に、豊富な手紙を引用しながら作家中條百合子(
後宮本百合子)との恋愛と
ソビエト留学期間も含む二人の共同生活を描き、昭和戦前期に女二人が共に生きることについて書かれたノンフィクション。百合子だし百合だしここに置いてもいい、よね。京都に生まれ、養子に出された家で膨らみ始めた胸を養父にまさぐられ、母に訴えても男はそんなものだといなされた経験から養家を嫌ったり、思ったことは率直に言ってしまう強烈な自我、個性を持つ
湯浅芳子。彼女は流行作家
田村俊子との関係や芸妓北村セイとの恋愛の後、
野上弥生子の元で百合子に出会う。そうしてロシア語の勉強と百合子との関係を深めていく。
1924年に出会って1932年に百合子が
宮本顕治と結婚するまで、
1920年代、百年前の
レズビアンカップルのドキュメントともいいうるけれど、芳子は同性愛者と言えても百合子は必ずしもそうではない。かといって女友達というわけでもない。まだ名前のない「名のない愛の生活」だった。本書はまず百合子との出会いから語り起こされ、その頃夫との関係に悩んでいた百合子は芳子との「新しい愛」に希望を見出す。「程度の差こそあれ、男の御意のままになる手近い女、という以外の敬意を払われて夫婦生活をして居る女が幾人あって?」(34P)と当時既に人気作家で経済的に夫に依存しているわけではない百合子が書いている。「芳子は百合子の眼の前に、男女の関係が必然的にはらむ支配と従属の問題をはっきり指摘して見せた」(46P)、それは芳子が
レズビアンという、「女らしさ」「男らしさ」の規範から外れた存在だったからだ。そうして始まる二人の生活の第一条件は、「一緒に居て仕事をすること」だった。お互いが尽くすのではなく、高めあう生活、それが二人の理想となった。しかし、
自分たちの愛は男と女のように結婚制度に守られているわけではない。外目には仲のいい女友達の共同生活と見られ、闖入者を防ぐ手だてはない。芳子はたえず外から自分の恋人が狙われているような気分におびやかされる。そこで頼りになるのは相手の気持ちだけだ。しかし、百合子はふたりの間柄を野上弥生子のような親しい人にも取り繕おうとする弱さがある。(70-71P)
「百合子が「女」より「男」を大切にする考えの持ち主であった」33Pとも指摘されている。
エロスの部屋を開ける「鍵」が芳子の手中にあることを知っていながらうながせない百合子と、「鍵」をもちながら開けようとしない芳子。どちらも「鍵」は「自然な男」が開けるものと思い込んでいる。(208P)
と二人の関係が描かれていて、この二人の生活には「制度」としての弱さと異性愛を「自然」と考える傾向という二つの弱さがあったと見える。事実、芳子自身の述懐として、二人の間にはないこともなかったけれども、性愛的な結びつきは薄かった旨の言葉もある。お互いの愛にはややズレがあった。民間の女性としては初めてソビエトに行くことになる直前も、芳子が暴力を振るったり、かなり関係は難しくなっていた。百合子の父の知り合いが日露協会会長だった後藤新平で、彼に頼んであっさりと許可をもらってモスクワに着くけれども、百合子は黙って片山潜と会うなど、思想にもズレが大きくなっていく。利己主義者で「女」の問題を考え続けた「自覚しないフェミニスト」湯浅芳子と、社会主義ソビエトを理想化し愛他主義的で「女」らしい愛想の良さを見せてしまう百合子とで、さまざまな違いはもちろんあった。それでもその違いを超える愛情の強さが二人の間には確かにあった。著者は、「男らしさ」に跪いてしまう百合子とされる側に自分を置こうとする芳子の二人の様子から、「男社会が女に課す女性嫌悪の装置」の存在を抉る。女性だけの生活だからといってそれとは無縁でいられるわけではなく、強固な性差別が女性自身にも女性嫌悪を内面化させてしまう。それでも、本書はお互いがお互いから得たものが何かを指摘する。
百合子が芳子にもらったものは、何よりその独立心と女としてのプライドであった。「男」との関係がいやがおうにも引き出す女の弱さ、それに打ち克つ術を百合子は芳子との生活の中で手にしたはずであった。
――中略
芳子が百合子にもらったものは、向上心と不断の努力、それらのもたらず自信だ。あきっぽく、ともすると無為に流れがちな芳子が、百合子の存在なくして自分のライフワークを見いだせたとは思えない。
――中略
ふたりは社会が女に押しつける、あらゆる不条理に手をたずさえて挑み、自らの全体性をまるごと取り戻そうとしたのである。(286-7P)
著者は芳子に人生で愛した人を三人挙げるとすれば誰か、と訊くと「百合子。それから、セイの順やな。三人目からは同じようなもんや」と答えたという。湯浅芳子のなかでの百合子の存在の大きさが窺えるエピソードで、本書の描くものが湯浅芳子の青春だという所以でもあろう。1990年2月刊の文藝春秋版の本書が出た八ヶ月後に芳子は93歳で亡くなる。多々引用されるように宮本百合子は『伸子』はじめ自伝的な小説で二人を描いているけれども著者は「歪められ」ているとやや批判的だ。湯浅の側からの証言を多々含んだ本書はその意味で貴重な一冊だろう。余談だけれど、ロシアでのエピソードはいろいろ面白くて、秋田雨雀や米川正夫と会ったり、彼らにも直言をして顰蹙を買ったり、あるいはトルストイの末娘がレズビアンで女性の恋人を伴って二人と出会ったエピソードなども面白い。学生時代の芳子の知り合いが五人も自殺した、ということに当時の女性の置かれた厳しさが窺える記述などもある。湯浅芳子がロシア文学を志したのは、ドストエフスキーを読んで、ということで、前項との奇妙な繋がりがある。