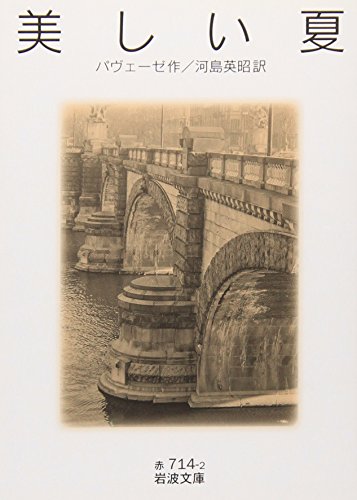いつかもやったページ数薄めの本を集めて読んでみるシーズンふたたび。
薄い本を読む - Close To The Wall
前回のは一昨年。今回はあとがき解説などを含めない、本文200ページ以下の本、というレギュレーションでやってみた。マルクスはよくわかんなかったけど、だいたいどれも面白かったですね。
薄い本はいいね、よくわかんなくてもすぐ読めて気分を切り替えられるし、短いなかにもぎゅっと詰まったものがあるのはなんかお得感がある。でも、薄い本ばかりだからもっと数読めるつもりだったのに思ったよりずっと時間が掛かってしまったので終わりです。このレギュレーションで積み上げた本がここにあるのよりも多く残ってるのでそのうちまたやるつもりはある。15冊。
戦争への機運が高まりつつあるなか、五〇歳前後の人々の皮膚に白い斑点が現われ死に至る
感染症が流行していた。ある医師が有効な治療法を発見するけれども、施術の条件として彼は平和を求め、戦争を準備する国の重要人物らに死か平和かの選択を迫る、SF戯曲。貧しい中国から生まれたとされ、五〇前後の人間を死に至らしめるけれども若者には感染しないという「白い病」の設定は非常に予言的で、作中でもこの病気が若者に場所を譲る機能を持つことによる世代間の対立が描かれている。疫病と戦争がともに人々を通じて感染していく時代状況の描写にもなっていてこれはまったく過去の話ではない。そこで現われるガレーン博士は治療の条件に戦争への反対や恒久的平和条約の締結を要求する、つまり命を取引材料にしている。著者が「ある種の平和のテロリストである」という通りだ。作者による前書きでは、この人物についてこうある。
また、人間愛と生への敬意という名の下でその男と戦っている人物は、病気に苦しむ者たちへの手助けを拒む。かれもまた、譲歩できない倫理の戦いを宿命として引き受けているからである。 この戦いで勝利を収めるには、平和や人間愛を掲げていたとしても、殺し合いをし、大虐殺で命を落とさなければならない。戦争の世界では、平和それ自体が、譲歩しない、不屈の戦士となる。159P。
しかし結末に見るように、こうした悲劇的な対立こそが作者の批判するものでもある。さらっと読める150ページ程度の戯曲だけど、感染症をめぐる問題とともに「戦争万歳」という熱気が人々に感染し、その拡大は指導者の命運をも脅かす危うい群衆の問題が重ねられていて、医療と政治の問題を疫病とそのメタファーを用いて描いている点が八〇年という時代を超えて生々しい。
疫病で人類社会が崩壊して60年後、盛期の文明を知る最後の老人が当時の状況をその孫たちに語り聞かせるポストアポカリプスものの表題中篇と、人口が増大した中国の脅威を
化学兵器で殲滅する短篇、そして食料を求めた人類史についてのエッセイを収めるSF的な一冊。チャペックの『白い病』は疫病の流行当時を描いていたけど、これは疫病による人類社会の崩壊後に現在時を置いており、チャペックが疫病と戦争を重ねていたのに対し、エッセイにあるように、ロンドンは戦争は将来的に消え、人口増大での過密による疫病の流行を予測していた。三作を通じて人口の増大が危機として通底していて、
感染症は集住し過密した人々を襲うものという認識がある。
黒死病を意識した「赤死病」は、発症から十五分で死に至るという強烈な死病で、避難し立てこもる場所でも感染し人間同士もまた殺し合い、人間はどんどんその数を減らしていった。2013年に
パンデミックが起こった設定で、それから60年後の現在時、一度人類が破滅の危機に瀕した後、辛うじて孫たちが生まれるようになってはいるけれど、老人と子供では知識の面でも溝が深く、話が容易に通じなくなっている。文化が途絶えているわけだ。言葉の断絶はもう一作でも出てくる。解説ではそうは言われてないけど、やはり「赤死病」では野蛮への蔑視があり、教育もなく粗野な「
おかかえ運転手」が元の主人たる少女を手籠めにしたあたりの話は、階級社会への批判とも読みうるけれども、「野蛮」という言葉の使い方には文明が失われたことへの慨嘆のほうを感じる。エッセイ「人間の漂流」には「黄禍」の語が出てくるように、中国の人口増大を脅威として描く「比類なき侵略」は黄禍論SFといえる。「世界と中国との紛争がその頂点に達したのは、一九七六年のことであった」と書き出されるこの短篇はまた現在の中国の存在感を予見しているようなところがある。この短篇では中国の脅威は多産による十億にならんとする人間の多さにある。序盤、中国は西洋とは別種の文明で、日本という中間的な存在あってはじめて「覚醒」し、「回春」したとある。そして多数の中国人が移住した領土を奪取し、世界を侵略していくのに西洋がどう対処したか、というSF。百年前のSFでなかなか面白いし、東洋をどう見ていたかという観点でも興味深く、じっさい予見的でもある。
マルサスに言及し、
社会主義を支持するエッセイも作品の背景を明らかにしていて興味深いもので、プラスの意味でもマイナスの意味でも面白い一冊。「
黒死病」に対するチャペックの白、ロンドンの赤。
晩年の講演録で、領域内で暴力を占有するものとして国家を定義づけ、権力の配分をめぐる努力が政治だという規定をしつつ、政治家と官僚についての対比を経ながら、政治家に必要なものは情熱と仕事に対する責任と距離を持った判断力だ、と述べる。「すべての国家は暴力の上に基礎づけられている」という
トロツキーの言を引きつつ、
ヴェーバーは
国家とは、ある一定の領域の内部で――この「領域」という点が特徴なのだが――正統な物理的暴力行使の独占を(実効的に)要求する人間共同体である、と。9-10P
と言う。これはよく知られた定義か。当時の革命騒ぎに対してヴェーバーは、自身の理想をのみ言って結果責任を人々のせいにする革命家を法螺吹きだと強く批判していて、そうした情熱的な「信条倫理」とともに結果に対する責任を負う「責任倫理」が両方あって初めて「政治への天職」を得ると述べる。政治には、暴力によってのみ解決できるようなもの課題があり、「魂の救済」を危うくする行いだとも言う。政治家とは、現実がいかに愚かで卑俗でも、「それにもかかわらず」といえる人間でなければならない、と言って終わる。指示に従うべき官僚の特質が政治家の資質としては最悪なものだという話もあったりして、官僚制の歴史なんかもある。節々のヨーロッパ独自のものという指摘は今でも正しいものなのかどうかは疑問に感じるけれども、古典的な政治家論としてなるほどこういうものなのか、と面白い。
講談社学術文庫の新訳、この時期の
フランス史よく知らないまま読んだら見事に撃沈した。
マルクスでは難しくない方らしいとはいえ、当時の政治状況をめぐるジャーナリスティックな文章なので、基礎知識は要る。
ユクスキュル、クリサート『生物から見た世界』
限られた知覚器官を持つ虫や動物が環境をどう見ているのか、を単に存在している「環境」という言い方ではなく、それぞれの生物が意味づけた主体的現実を環世界という言葉を用いて説明した一冊。もとは絵本として出版されたもの。文中にも出てくるけれど、ユクスキュルは
エストニア出身の
生物学者で、弟子筋にあたるクリサートが挿絵を描いている。ダニ、イヌ、ハエその他、それぞれにとっては同じ物を見ていてもまったく違う現実があり、「いずれの主体も主観的現実だけが存在する世界に生きており、環世界自体が主観的現実にほかならない」といい、このことは人間同士でもそこを初めて訪れるのと地元のものとで環世界が違う、とも論じる。確か文中にカントの引用があって、19世紀の
生物学者は哲学者を引用するんだなと思ったけれど、それぞれの主体は「環境」を別様に見ていて、そしてその向こうには永遠に認識されない「自然という主体」を示すところなどは、確かにカントの「物自体」の議論が踏まえられているのか。
フリップフラッパーズというアニメに出てくる小さい生き物がユクスキュルと名づけられていた縁で、その筋の人には知られた本だけど、じっさい
フリップフラッパーズのキャッチコピーには「あなたには、世界はどう見えているんだろう」と書かれていて、直接の影響が感じられる。
表題作は小説の腹案が
ナボコフの先行作品と似ているからと辞めたら
ナボコフにそんな小説はなく夢で見たのではという話から、自分の執着する樹の影の謎が、妄言とばかり思った老婆の話によって己の現実を突き崩す出生の真相が引き出されるかのような現実と夢の入り交じる幻想的中篇。小説家を主人公にした小説を書く小説という形式に
ナボコフや
エドナ・オブライエンという実在の作家の名前なんかも差し込みながら、現実だと思ってたら夢で、妄言だと思っていたら真実では、という複層的な虚実反転を決める技巧性があり、そしてPKディック的崩壊感覚を思い出す。小説家が小説家を主人公にして、という形式的なメタ性も含めると相当多層的になってて、面白いし技巧的で、まあ、こういうのみんな好きだよね。本書は表題作と他二作を収める短篇集で、ほか「鈍感な青年」「夢を買ひます」という作品が入っている。「鈍感な青年」は初々しい恋人同士の初体験をめぐる短篇だけど、デートで行こうとしていた、あるはずの祭がない、という現実性の揺れみたいなものも描かれていて、「夢を買ひます」も整形をめぐる思い込みの話とともに、夢が真にという要素があり、緩やかに連繋しているように見える。
都会で働く16歳の
ジーニア、三つ上で画家のモデルをしているアメーリアと、絵描きグィードとロドリゲスという男女四人を描きながら、
ジーニアのグィードとの恋愛とその終わりを通じて、女二人、作者いわく「レスビアンの娘たちの物語」でもあるというイタリアの作家の長篇小説。軽く見ていた友人達がすでに男たちとの関係を持っていたことがわかる序盤の、
ジーニアの優越感とじっさいは取り残されているという若者らしい描写や書き出しの情感も良くて、それが、解説によると
ファシズム政権下の様子を微妙に滲ませた夏のイタリアを舞台に語られる。
ジーニアとモデルをしているアメーリアとの関係が、裸体モデルをしているところを見たい、ということでアトリエに一緒に行くあたりで深まっていくんだけれど、ここで明らかに
ジーニアの興味がアメーリアにあるあたりで、あれこれは百合なのでは、と思ったら前述作者のコメントを全面的に受け入れるには留保がいるけれども、実際そういう面もある。知らないことを教えてくれる年上のアメーリアへの憧れとともに、同じ男をめぐる微妙な心情があり、アメーリアからもキスや、「わたしは、あなたに恋をしているの」と来るなど、彼女は同性愛者でもあるだろう。それも含めて四人の関係はなかなかわかりづらいところがある。長い解説が丁寧に作品を分析していて、ある人物に反
ファシズム闘争のニュアンスを見たり、二人の女性の関係を未来と過去としてお互いがお互いを見ている相互的なものになっているというのはなるほど面白いし、ラストシーンのセリフもそういうニュアンスがあるのがわかる。主人公が16歳から17歳になる夏から冬にかけてを舞台にした、同性異性それぞれへの感情を絡めて、少女から大人へとかわる様子を描いた青春小説といってよく、短い長篇ながら明示的に描いていないところも多くて読み込む必要が結構あると思う。今作は『丘の上の悪魔』『孤独な女たちと』で三部作を成すらしい。
パリ郊外についての小説や写真集などをめぐる考察を、仮構された「私」を通して語る一冊。郊外小説を語るためにパリ在住の壁の内と外を歩き回る架空の「下等遊民」と挿話を土台に語るという方法を用いた独特の散文作品。小説とエッセイのあわいの読み心地がある。Uブックスで「エッセイの小径」とあるのに、一連の物語に出てくる「私」とその周辺の出来事は完全に虚構だとぬけぬけと語るあとがきに、小説の萌芽ともいえるものがあるのは確かで、事実、冒頭の一篇
からして語りの距離感はいわゆるエッセイとはやはり異なる。最終篇の「コン
クリートと緑がたがいちがいに出現する異郷の郊外地区の風景を、私はいわばクッションボールで処理しようとしていたのであり、間接的な仕方でしか見えてこないものを追い求めていたのだ」(186P)というくだりは種明かしをしている箇所だろうか。小説を論じる連載を書きあぐね、虚構の「私」という小説的方法を用いることで書き進めることができたようで、おそらくこれは小説のように書くことで小説を語るという試論ではないか。あとがきでも「小説」とは述べていない。どちらでもありうるし、どちらでもないかも知れない。内容としては、フランス語に訳された他の外国の文学を読んでみるという「受容の受容」を、文化の模倣吸収をめぐって、どこか都市と郊外の関係に似たものをそこに認めつつ、それが「くつろぎ」を与えるのは、第三国の者として傍観者の無責任があるゆえだと語るところや、
ナチスの
ユダヤ人収容所に転用され、戦後はナチへのコラボが収容されたあと、今は郊外人を「収容」している、という郊外団地や、
ペレック『僕は覚えている』や
セリーヌの文章が郊外の生徒からさまざまな表現を引き出したり、
カフカの断片の続篇を書いた生徒がいたという本の話などが印象的だ。フランス郊外の地理が全然わからないので地図が欲しかったけど、ごく単純に楽しい散文として面白く読める一冊で、
堀江敏幸のデビュー作としても興味深い本だろう。私は『熊の敷石』をずいぶん前に読んだきりだった。マルト・ロベール訳
カフカの文庫本というのが出てくるけど、そういや
丸谷才一「樹影譚」にもマルト・ロベールが名前を出さずに言及されていた。言及されるモディアノの『特赦』は『嫌なことは後まわし』として訳されている。
軍艦から転落して十日間を漂流して生還した水兵の物語を新聞記者時代の
マルケスが
聞き書きしたという一冊。漂流の苦難を生々しく描き出すドキュメンタリーだけど、
マルケス研究でも評価が分かれ、事実か脚色かにわかに判然としないところがある。内容としては
ヘミングウェイの『
老人と海』にも似た海洋漂流譚で、飢えと渇き、サメの恐怖に怯えながらの十日間の漂流は非常に小説的な迫力がある文章で、これが
聞き書きだとはなかなか信じにくいところもある。『
百年の孤独』の三年後に書籍化されたため、読者の幻滅を招いたこととドキュメンタリーゆえに空想に制約があるという評価に対し、これは『
百年の孤独』の大ブームという狂騒に巻きこまれた
マルケス自身を生還した英雄の水兵に託して語ったもので、
ホメロスの『
オデュッセイア』を下敷きにした箇所や沈んだ水兵らに実在の作家たちをモデルにたところがあるという読解がされてもいる。この文章がじっさいに1955年の新聞に発表されたことは事実らしいけれども、書籍化されるさいに改稿された可能性も訳者は指摘していて、これは決着がついたんだろうか。ともかく、
マルケスらしい小説を期待して読むものではないとも思うけれど、事実かフィクションかという解釈を問われるところがある。まあそういう二者択一というよりはどっちでもある、というほうがありそうでもある。表紙には長いタイトルが記載されていて、これが正式タイトルなんだろうか。「飲まず食わずのまま十日間筏で漂流し、国家の英雄として歓呼で迎えられ、美女たちのキスの雨を浴び、コマーシャルに出て金持ちになったが、やがて政府に睨まれ永久に忘れ去られることになった、ある遭難者の物語」。いかにも古典文学的な長文題、というか『
ロビンソン・クルーソー』を意識しているのかも知れない。
図書館の非正規職員をしている女性がある日コンサートで
ブルックナー団を名乗る男性たちと出会う。垢抜けないオタクとしての彼らと、批評家に攻撃された
ブルックナーの不器用でモテないエピソードを重ねつつ、夢への思いを鼓舞する青春小説のおもむき。
ブルックナー団のなかなかにひどいオタク仕草や変な語尾で喋るやばいヤツの痛々しさを描きながら、団員の一人がサイトに上げている
ブルックナーの伝記を作中作として挿入し、それについての主人公の感想を挾みつつ、この
ブルックナーオタクと
ブルックナー伝記の二軸で進んでいく。
ブルックナーのことは全然知らなかったけれど、処世下手で人情の機微に疎く、才能がありながらも疎まれ、それでいて厚
かましい面もあってこれはなかなか、と思っていたら「嫁帖」の話は女性への態度がヤバすぎて、同情も吹っ飛ぶレベルなので主人公のコメントは正しいな、と思った。伝記を書いてる団員は小説も書いているけれど自己陶酔的な欠点があり、自分と距離のある人物や事実を元にするといいものを書く、とも言われていて、この書くことに客観性を取り込み良いものにするためという方向とともに主人公の自己を客観的に見過ぎてやりたいことを諦めた情熱の復活をも描いている。
探偵ブルーが依頼者ホワイトからブラックという人物を調査して報告書を週一で書いて欲しい、というところから始まる、探偵小説の構成を借りた、書くことと読むことをめぐる
アイデンティティの不安、を描いた感じの中篇。色と記号的な名前、文字や紙を思わせるし、孤独な部屋で書き物をしているので、あからさまに書くことが意識されている。
柴田元幸が「エレガントな前衛」と呼んでいるように、前衛的な小説はパワータイプが多い
アメリカ文学には珍しいらしい。書くこと読まれること、見ること見られること、探偵小説の構成を借りた
メタフィクションの手触りは確かに
安部公房を感じる。ニューヨーク三部作の第二作。オースター、二〇年前には既に人気作家だったしその頃から読むつもりはあったし、これも買ったのは結構前なんだけど、今更初めて読んだ。三部作と何かしら代表作を読んでおきたい。
ボルヘスの盟友として知られるアルゼンチンの作家の1940年作。
政治犯受刑者の語り手が逃げ込んだ孤島に、突然複数の男女が現われ、その一人の女性に惚れ込むけれど、なぜかいっさい反応が得られず、そんな時島には二つの太陽、二つの月が現われ、というSF
幻想小説。SFとしては古典的な設定にも見えるけど、ネタが明らかになるまではこれはどっちだ?となるところがあるし、この愛をめぐる解釈を誘う設定はやはり面白い。なるほどねと思って解説を読むと、一人称での叙述に時間の矛盾があると指摘されていて、やっぱそんな簡単じゃないなと思わされる。最初語り手の名前がモレルだと思ってたけどあ、違うのかと思ったらやっぱり同一性は確実に意識されている。解説にある
ボルヘスのトレーン~の冒頭の記述が本作のことだとして、一人称の矛盾があることがどういう読みを引き出しうるのか、と思ったけどモレルと語り手について、だろうか。分身、鏡、愛、不死、他者その他いろいろ……。後の作品にも影響を与えているようで、そういう意味でも早く読んでおくといい気がする。序盤やや退屈ではある。帯文に「独身者の《機械》」とあって、そういやちょうどこの前買ったカルージュ『独身者機械』にカ
サーレス論がある。それだけ拾い読みしたけど、受刑者という属性から
カフカの「
流刑地にて」と繋げたり、舞台がエリス諸島のヴィリングス島というのは疑わしいという刊行者注に着目して、ここにモレルがmort=死者、ヴィリングスがLivings=生者、エリスのフランス語から無限などの言葉遊びを引き出してたりしてなかなか面白い。
ブストス=ドメックやイシドロ・パロディとか、
ボルヘスとの共著はいくつか読んでるけど、カ
サーレスの単著は初めて読んだ。しかし書くことと幽霊というとオースターの『幽霊たち』みたいだ。持ってるのは90年代に出た叢書
アンデスの風版。確か池袋
ジュンク堂で買ったはず。2008年に再刊されている。
清水徹が
ブランショ経由で読んでいたのがきっかけらしいけど、専門外の言葉、というから清水は仏訳も参考にしつつ、ちゃんと
スペイン語からの翻訳をしたのを
牛島信明が
校閲した、という形か。清水には『鏡とエロスと』という日本文学論集がある。
日々、爪、夢、切り抜き、希望など、12のコレクションにまつわる不穏な掌篇連作と、
ティーショップで物語のお茶を注文すると店内の人々が次々に物語を語り継いでいく短篇を収めた
セルビアの作家の作品集。
ボルヘスの盟友カ
サーレスに続いて、「東欧の
ボルヘス」と帯にある
ジヴコヴィッチの
ボルヘス繋がり。ただ、あまり
ボルヘスぽくは感じない。「12人の蒐集家」は有形無形さまざまなコレクションが概して終わり、消滅とともに語られていて、ある日の記憶を代償に素晴らしいケーキを食べられるけれど食べすぎると消えてしまうという話や、切った爪を丁寧に保管してコレクションしているけれど、死んだら自分のコレクションがどうなるかと不安になる話、とつぜん現われた男がピアノや隕石などが落ちて死んだ不幸で希有な運命の
人間について語ったかと思うとサインを求められ、あたなはこれから有名になる、と言われる話などが語られる怪奇掌篇集。一篇一篇はわりあいに軽妙なさらっと読める幻想
怪奇小説になっている。それでいて、集めることがそのまま消えることへと転じていくような連作にもなっていて、この反転性が解説にもある
ジヴコヴィッチの魅力だろうか。黒田藩プレスから出た作品集にも入っていた「
ティーショップ」は
千夜一夜物語を思わせる、物語が物語を呼び寄せ、語ることがさらなる語りを生み出す短篇。ある旅人が
ティーショップに入ると「物語のお茶」というメニューに目が止まり、それを注文すると店員はおろか客席にいた人々までが次々に物語を語り出していく、
フラッシュモブみたいな展開が楽しいのと、語りのギミックが決まってて再録も納得の短篇だと思う。黒田藩プレスのも『時間はだれも待ってくれない』収録作も読んだので、あと一作80年代の
SFマガジンに載ったものが既訳としては未読。洒落てていいけど軽め、という印象なので
世界幻想文学大賞受賞作のThe Libraryとか、長めの作品も読んでみたいところ。長篇型の作家ではないのかも知れないけど。
セルビアの作家だけれど本書は英訳からの重訳。英語版
Wikipediaを見ると、The Writer、The Book、The Library、Miss Tamara, The Reader、The Last Book、The Ghostwriterとか、本にまつわる小説がたくさんある。ここら辺が
ボルヘスが引き合いに出される要因かも知れない。
Zoran Živković (writer) - Wikipedia