
- 作者: 後藤明生
- 出版社/メーカー: アーリーバード・ブックス
- 発売日: 2014/04/12
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る
じつは「デビュー作」というのもちょっと不正確で、後藤明生の実質第一作となると学生時代に「第四回全国学生小説コンクール」入選作として「文藝」誌に掲載された1955年の「赤と黒の記憶」がある*1。「関係」は1962年で、間に七年の空白があり、そこにまた一作、読売新聞主催の短篇小説賞に応募して落選したものの『読売短篇小説集』(文苑社、1959年刊)に「丘の上」として収録された「異邦人」がはさまる。おそらくこれが後藤明生作品が単行本に収録されたものの最初だろう。以下参照。
TRCブックポータル 「後藤明生」で検索した結果
ここには単著発刊以前に後藤明生作品が収録された三作のアンソロジーがあり、読売のものと、文藝賞のもの、そして「文學界」の同人雑誌推薦作の枠で転載された作品を集めたアンソロジー『新文学の探究 全国同人雑誌ベスト12』があり、これには後藤明生が同人雑誌「犀」に発表し、「文學界」に転載されて、以後中央の文芸誌で活躍するきっかけになった「離れざる顔」が、向井豊昭の「うた詠み」とともに収録されており、当ブログとしては非常に興味深い。
http://www.bookportal.jp/product/02589951
ここらへんの情報、『日本近代文学との戦い』所収の現状最新の年譜にも載っていないのは、省略されたのだろうか。でも、著作目録にも載っていない。
「赤と黒の記憶」「異邦人」「関係」の三作が後藤明生のデビューに至る軌跡としてあるけれど、『関係』の後書きには二十代で書いたのは「これが全部というわけではないが」と書かれており、未発表作かなにかがあるのだろうか。
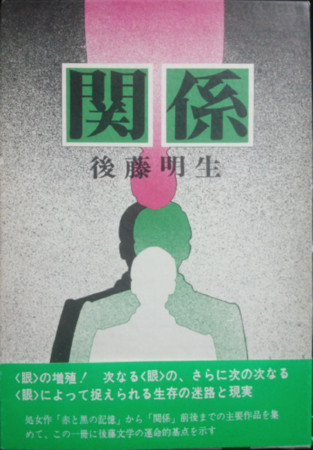

- 作者: 後藤明生
- 出版社/メーカー: 皆美社
- 発売日: 1971
- メディア: ?
- クリック: 11回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
デビュー作というのもあるけれども、つまりそれだけ後藤明生にとって重要なものだからだろう。集英社文庫の『笑い地獄』には、底本収録作にやや時期の異なる「関係」を追加していたり、自選短篇集に入れているのもこだわりが見て取れる。ツイッターで旺文社文庫版の年譜から引用されている(同じ旺文社文庫の『四十歳のオブローモフ』にこの記述はない)ように
冒頭からして、かなり攻めているのがわかる。
西野は北村に弱味を握られていると思っている。北村はああいう男だから年の二十九歳にもなれば社会的信用などというものを考えているにちがいないが、その彼の考えているおれの社会的信用というやつを、やりようによってはゼロにたたき落とすことだってできると北村は考えているにちがいない、そんなふうに西野は思っているのだ。(皆美社『関係』7P)
と言う風に語り手「井上淳子」は考えている、という非常に面倒な入れ子構造的な情報が冒頭からどばっと押しよせてくる。一読理解が行き届かないような「関係」と各人の理屈を推察してみたりするんだけれど、結局は「西野は北村の腕力をこわがっている」、そんな男として、ふてぶてしく「スケコマシ」と呼ばれる西野が提示される。
今作はこの西野と「関係」を持っている井上が、北村から、西野と結婚するか「関係」を解消するかするべきだ、と言われ、北村は不誠実な西野への怒りを露わにしている、そんな三角「関係」のごたごたを、雑誌編集の仕事を舞台にして展開していくことになる。
つまり、肉体「関係」や三角「関係」、そして不倫「関係」といったいくつもの「関係」と呼ばれるものがタイトルには掛かっていて、誰と誰がどんな関係で、そんな関係を誰が知り誰が知らないか、そういった関係の仕方をさまざまに描き出しているのがこの短篇となっている。
西野と北村という対面したことのない二人に挾まれる形になる語り手井上の視点から、この事態は冷静に眺められるのだけれど、渦中の人物のはずの語り手は自身の感情をあらわに書くことはせず、肉体関係の成立や二股の告白にも特段その感想を書かない、というきわめてストイックな語りになっている点も特徴的だ。作者唯一の女性人称小説なのに、というよりはだからこそ、この語りが選ばれている。「関係」の中心としてつねに眺められる側としての女性の視点を用いることで、男性目線の関係を裏返して、すべてを冷静かつ皮肉に観察することができるからだろう。
とはいえ、作中登場人物に対する観察や批評はなかなか鋭く書かれており、北村を頭の悪さを露呈してしまう、いやな野郎だ、とか書いたりして、辛辣だったりするんだけれど、そんな北村と後々不倫してたりするのがどうにも皮肉で、そういう展開になるあたりの語り手の感情は隠されていて、それもまた狡猾な書き方ではある。
作中様々な関係のあり方、関係しないという関係の仕方、といったいろいろな人たちの存在の仕方が描き出されており、冷徹かつメカニカルな関係の描写は非常に今読んでも実験的な印象が強く、面白い。言ってみれば職場での三角関係や肉体関係のどろどろが素材で、それだけならまあ情感的だったり、風俗的だったりする、都市の現代的な雑誌編集者の生態みたいな小説はいくらも書かれているだろうけれども、そうした要素をほとんど排除して、こんな作品が書かれるというのはひとつの驚きを与えたんではなかろうかと思う。妙に理屈くさいうえに、その理屈がなんか奇妙なのはやはり後藤明生らしい。
さらに、ある事実が語り手の頭に衝撃を与えた、という比喩的な描写が、じつは本当になぐられて頭が痛かった、というなんだそりゃ、と突っ込みたくなるような話の切り替え方は、読んでいるこちらのイメージを一気にひっくり返す後藤明生得意の手法だ。前回とりあげた「書かれない報告」でも虫を殺す目覚ましい一場面が読者を驚かすような記述になっていて、こういう鮮やかな転換の妙が印象的だ。
この作品については、後藤自身が『関係』のあとがきでも書いており、それは全文引用したいような興味深い記述で、「関係」が自分にとって、「現実とはこんなものだ」という自覚に基づいて書かれた最初の作品で、それは現実というものの普遍的構造を見出した、という意味合いだろうけれども、その眼で捉えられた人間は「内部」が剥奪捨象されており、その捨象された「内部」は「笑い」という「もう一つの〈眼〉」でもって造反した、と自身の作家的変遷を語っている。そしてこのように続ける。
〈眼〉の増殖! それはわたしにとって、他ならぬ『関係』の〈眼〉をのりこえるべき、次なる〈眼〉の、さらに次の次なる〈眼〉の増殖だったのである。そしてそれは、およそ無限定に、果しなく続けられるわたし自身の戦いであるという意味において、『関係』はわたしの運命的作品といわなければなるまい。『関係』との無限の戦いこそ、わたしの運命なのだ。(皆美社『関係』220P)
後藤にとっての「関係」の重要性は、ここら辺だろうか。方法的な自覚に基づいた最初の作品にして、後の作品の基礎として常に否定的参照項としてあった、という。「笑い」の導入、そして「団地」はこの、「〈眼〉の増殖」の一例でもあるだろう。
そう言う意味でも、作品としての面白さ奇妙さでも、やはり後藤作品中非常に重要な作品でもある。
しかし、まあ上掲引用部分でもそうだけれど、後藤明生って本当に「戦い」が好きだ。ここまで戦闘的な言葉で日常やら自身の文学的あれやこれやを語る人というのも珍しいのではないか。後藤作品ではどうでもいいような些事に対しても、大げさで敵対的な線を引いて、闘争心を露わにするような場面がしばしばあるわけだけれど、日常のなかで戦闘的体勢をとることの奇妙さという笑い、というのが一点には目論まれているということの他にも、兵隊になれなかった戦中派少年にとって、この戦いということは何かしら意味があるようにも思う。芳川泰久は「不参戦者の戦い」というようなことを言っていたけれども。
で、思ったんだけれど、これは横光利一の「機械」を下敷きにしていないだろうか。