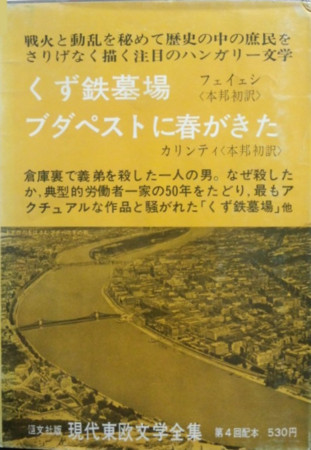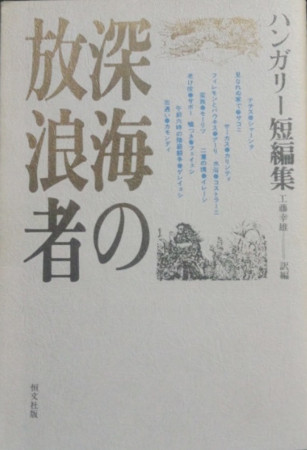- 出版社/メーカー: 恒文社
- 発売日: 1966
- メディア: ?
- この商品を含むブログを見る


- 作者: カリンティ・フィレンツ,上村ユキ子,羽仁協子
- 出版社/メーカー: 恒文社
- 発売日: 1971/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
徳永康元・羽仁協子「現代ハンガリーとその文学」……3P
フェイェシ「くず鉄墓場」羽仁協子訳……27P
カリンティ「ブダペストに春がきた」上村ユキ子訳……169P
エルデーシュ「私の解放された日々」羽仁協子訳……363P
メーセイ「脱出」羽仁協子訳……385P
木島始「わたしの作品論」……403P
月報
「西欧化とインターナショナリズム」針生一郎
「ブダペストの街」編集部
フェイェシ・エンドレ - くず鉄墓場 Fejes Endre(1923-)"Rozsdatemető"1962
フェイェシはブダペストに生まれ、工場労働者の父親をもち、自身も中学を出て仕立屋の見習から旋盤工になっている。第二次大戦で両親を失い、熟練旋盤工として49年までEuropeを渡り歩いたという。ブダペストにもどっても旋盤工として働き、そのあいだに小説を書き始め、週刊紙の編集員にもなっている。第一短篇集『嘘つき(A hazudos)』が58年に刊行、そして、62年の『くず鉄墓場』が大きな評判を呼び、映画化もされた。なんと、Wikipediaで見た限り存命らしい。
『くず鉄墓場』は、ハーベトレルという一家のおよそ二代ちょっとの歴史を、第一次大戦のころから、1963年の春(つまり、今作刊行の半年後)までを舞台にして描いた作品だ。冒頭は、息子のハーベトレル・ヤーノシュ(父と子は同名)が一人の男をくず鉄墓場で殺した場面から始まる。そして、ある語り手が、彼の情報を収集し、そしてヤーノシュに話を聞いた挙げ句書かれたのが、本作だという体裁になっている。
そして始まるのは、父のハーベトレル・ヤーノシュがブダペストで彼の終生の妻となるペーク・マリアと出会った話だ。労働者一家ハーベトレル家の物語がここから始まるのだけれど、数十年の一家の話がおよそ200ページもないくらいの分量に詰め込まれており、くだくだしい説明を排除した文体で一気呵成に語られていく小気味よさがある。
労働者一家ということで、登場人物達がみな行動的で悪い言い方をすれば粗野なところがあり、切れやすい息子や一ページごとに恋人が変るような娘たち、そしてなんといっても肝っ玉母さんとでもいうべきこの小説の屋台骨ペーク・マリアがこの作品の核だろう。彼女の言葉よりも先に手が出る暴れっぷりは、ほとんどギャグのようで、遅く帰った娘を出会い頭にぶん殴るシーンにはその唐突なバイオレンスさに笑ってしまった。小説の始まりはハーベトレルと彼女との出会いだし、じつは一家二代の歴史というよりは、ペーク・マリアという屋台骨を持つ一家の物語というのが正しいように思う。労働者階級の、ある種典型的かつ破天荒な家庭生活を、嵐のようなスピードのなかでコミカルに描いた作品なのではないか。しかし、最初の殺人事件は息子ハーベトレルがアルコール中毒の義弟を殺してしまうという話なので、その悲劇にくるまれた物語として今作は語られる。
戦後社会主義体制になっても、人物たちの考えや何やらが特に変ったようには見えず、そうした政治的、社会的関心とはまるで別の水準で小説が進んでいくのも特徴的。親密な交流がある共産主義の夫婦がいるのだけれど、途中で仕事でイスラエルに行ったりするわりとエリート風の彼等に対しても、一家の皆は、その言動を笑ってネタにしているばかりだ。とはいっても、よく分らないことに熱中している子供を笑うような、笑いはしても嘲笑はしないような親密な視線での付き合いだったりする。
とはいえ、数十年のハンガリーの歴史が背景にあるので、所々に歴史的事件が書き込まれる。特に大きいのは、息子のハーベトレル・ヤーノシュ、通称ヤニの最初の妻、ライチ・カトーのことだ。彼女はユダヤ人で、ヤニは彼女と結婚し息子をひとりもうけるのだけれど、ヤニが戦争に出征しているあいだ、ブダペストから田舎に疎開したペーク・マリアら一家は、カトーとその子をブダペストに忘れていってしまう。そして、疎開からもどった時彼女たちの消息は途絶えていた。親ナチスで反ユダヤの民族主義政党、矢十字党が終戦間際に政権をとっており、特にユダヤ人が多かったというブダペストでは、この間かなりのユダヤ人が収容所送りとなっていた。このことは、母ペーク・マリアの痛恨の失策として、後にヤニから指摘される場面がある。
そして、もう一つはハンガリー動乱あるいは1956年革命がソ連の介入によってつぶされた時だ。労働者の家庭の視点から、なにかはよく分らないけれども、非常に不穏なことが起きているということが辛うじて分る、という書かれ方をしている。銃撃砲声が聞こえてくる、外出禁止の状況下で、なにかが起きている、という描写だ。
夜中、町の中心から銃声がした。翌日、エステルたちは、ラジオの呼びかけにしたがって一歩も外出せずに、うちにこもったきりで過ごした。夕方、思いがけなく、ヒーレシュ・イシュトヴァーンが訪ねてきた。ほこりにまみれた、しわだらけの服、ほてった顔、熱病患者のような目、それを見るなり、三人はきいた。町の中でなにが起こっているのか。革命が起こっているのだ、とヒーレシュは答えた。
――中略――
「ぼくはペテーフィ・クラブの一員なんだ。ぼくらがデモを決議し組織したんだ。ペテーフィ広場にも、ベムの銅像前の集会にも参加した。放送局にもおしかけた。そのときはじめて、ぼくたちは発砲されたんだ」127P(訳注を省略)
外出禁止が発令され、翌日の「木曜日」に娘が外出していることから、上記は1956年の10月24日のことだ。そして娘は外で死体を目にし、なにが起こっているのか分らないと混乱する。知り合いの共産党員もまた、どうしてこうなったのかと困惑しており、そして自分に感化されて党に入り志願して秘密警察アーヴォーに入った親類の子供が、この争乱のなかで死んだことをハーベトレルたちに述懐する。また、上記引用中のヒーレシュは、11月に外出したところ、銃撃され入院する。
ここでは、ハンガリー動乱がなにか、ということは説明されない。老ハーベトレルは、生まれてこの方政治になど興味を持ったことなどないと語るとおり、そうした方面からこの問題に踏み込むことはないけれども、周囲の人々は皆さまざまな形でこの「戦争」にかかわり、巻き込まれてもいる。

- 作者: 工藤幸雄
- 出版社/メーカー: 恒文社
- 発売日: 1966
- メディア: ?
- この商品を含むブログを見る
カリンティ・フェレンツ - ブダペストに春がきた Karinthy Ferenc(1921-1992)"Budapesti tavasz"1953
外は雪が激しく降っていた。オーバーにも頭の上にも雪がつもって、白く光った。夜が白みかけ砲火も一時鳴りをひそめていた。あらゆる破壊の残骸――爆弾のあけた大きな穴、ずたずたに引き裂かれた屋根、瓦礫の山、――そんな無残な光景を、うずを巻いて風に舞う新雪が少しずつ少しずつ覆い隠していった。279P
カリンティは二十世紀ハンガリー文学を代表するという作家カリンティ・フリジェシュの子として生まれる。けれどもフリジェシュの方は単著も長篇も邦訳書がなく、フェレンツは本作や不条理SF『エペペ』と、二つの長篇が訳されており、日本ではカリンティといえばフェレンツの方が有名かも知れない。そのフェレンツは第一長篇『ドン・ファンの夜』を1943年に刊行しており、これはシュルレアリスムの影響が濃いものだったのが、四十年代の終り頃から作風がリアリズムに変化していったという。五十年前後には劇場で演出家としても活動しており、評論、戯曲、モリエールなどの翻訳や、言語学、社会学など活動範囲は多岐に渡り、38年に亡くなった父フリジェシュの回想録なども書いている。そして、フェレンツはブダペスト大学で1946年言語学の博士号を取得している。これは『エペペ』が言語学者を主人公としていることや、本作の主人公も言語学を学んでいることに反映している。
本作は、1944年のクリスマスを前に、二人の人物が軍隊から休暇を得てそのまま脱走する場面から話が始まる。主人公ピンテール・ゾルターンとガジョー・ベルタランだ。なんとかして故郷ブダペストに帰ってきたのだけれど、その時都市はソ連軍の侵攻を受けており、日常的に砲撃されている真っ直中だった。実家に戻り、顔を合わせる主人公だったけれども、ここには住めないといわれ、親戚のアパートを紹介されそこに住むことになる。そこでは叔父トゥルノフスキ夫とその妻で、ユダヤ人だと言うことを隠しているイルマや、その姪クラーリ・ユトカらが住んでいた。ゾルターンはこのユダヤ人女性ユトカと恋に落ちる。
また、ガジョー・ベルタランの方では、旧友に出会い、その友人はコミュニストの地下組織に属しており、反ナチス闘争にかかわっていた。この頃のハンガリーは上述したように矢十字党のサーラシが政権を握っており、ラジオからも「サーラシ万歳!」の声が聞こえてくるという状況で、夜間の外出は禁止されており、見つかれば銃殺ものだと皆が認識していた。ソ連からの攻撃とファシスト政権による抑圧的統治という二重の圧力がブダペストを覆っている。コミュニストの地下組織リーダーはこう言う。
今は、ブダペストじゅうが地下の世界なんだ。266P
さらに、矢十字党によるユダヤ迫害が、身近な圧力として迫ってくる。アパートに住むトゥルノフスキ氏の妻は書類を偽ってユダヤ人だということを隠しているのだけれど、彼女を誘惑しようとして失敗した男がその腹いせに夫妻を告発し、ある早朝に矢十字党の捜索を受ける。これに恐れをなしたトゥルノフスキ氏は、姪のユダヤ人クラーリ・ユトカにアパートを出るよう言いつける。そして元住んでいた場所に戻ったクラーリ・ユトカは隣人に告発され牢に拘留される。
既に恋仲となっていたゾルターンはそれに驚き、夜間外出禁止のブダペストを走りまわる。そして、ユダヤ人だと見なされて収容された牢屋でクラーリ・ユトカと出会うのだけれど、彼が無罪放免されているあいだに、ユトカらユダヤ人たちは矢十字党に射殺され、おそらくはドナウに放り込まれただろうことを知る。
ゾルターンはその怒りからガジョーの友人が属するコミュニストの地下組織からの誘いを受け、市内のドイツ軍への破壊工作に身を投じることになる。砲撃で街中の建物は破壊され、時折の着弾での衝撃が伝わってくる中で、主人公たちは警戒体制のさなかの街を移動しつづける。そして破壊活動のなかでも内ゲバが起こって、ガジョーは捕まってしまう。砲撃と包囲、矢十字党による恐怖政治、またさらに地下組織内部での争い、と二重三重にも重なる困難がゾルターンたちを襲うわけで、リアリスティックな筆致で危機のさなかのブダペストを描き出している。
そしてようやく、彼等を解放するソ連軍がやってくる。ドナウを挾んで二つに分れているブダペストは、作中でも書かれているように橋を落されて、両方を解放するには時間が掛かった。ペストは一月十八日、ブダは二月十三日にそれぞれ解放された。クリスマスから始まり雪の降り積もる風景のなかで進行する本作は、解放という春を迎えるまでを描いている。
終戦直前のブダペストの空気がよく伝わってくる作品で、矢十字党の恐怖政治や砲撃が日常化した風景、ユダヤ人の告発・連行・殺害、地下組織の破壊活動といった概説書でも出てくる歴史的事実をうまく取り入れて構成されているようだ。フェイェシの庶民的視線から一貫して数十年を駆け抜けるような作風と対照的に、言語学を学ぶインテリよりの視点から、ブダペストの数週間を丁寧に描く本作とで、ブダペストを二つの視点から描き出すようになっている。
エルデーシュ・ラースロー - 私の解放された日々 Erdős László(1913-1997)
以下二作は原題と発表年が明記されておらず不明。今巻に限らず、このシリーズでの短篇は奥付に解説でも原題発表年が示されていないことがある。
今作は、ダッハウ収容所に送られた左派知識人の生き残りによって書かれており、上記二作でユダヤ人らが送られた収容所、その収容された側からの視点を提供している。語り手は作中で「エルデーシュ・ラチ」と呼ばれており、ラチはラースローのニックネームなのでノンフィクションなのだろう。作中に出てくる他の人名ももしかしたら実名かも知れない。タイトル通り、収容所生活とそこから解放されて、故郷に帰るまでを書いたものになっている。
ダッハウ収容所での生活の様子が細かく描かれており、憎み合っていた多くの民族同士が、収容所という場所で、極寒の風呂や拷問で死ぬことが多いために、チフスで臥せっているのはむしろ歓迎されるというような逆説や、ある種の距離感を保ちながらも、ふとしたきっかけから距離を縮めて連帯感を抱くようになる状況などの極限環境での論理が示される。ぼろぼろ人が死んでいく。
特に、語り手が露わにするのは、民族主義者への怒りだ。
私が生きのびられたのはいろいろな民族の間の連帯性のおかげだった。それだけに私は民族主義者たちの絶滅を願う権利がある。本当の愛国主義者たちは共通の敵に対する戦いによって結ばれ、人を助ける場合、その人がどこの民族の出身者であるかを意に介さなかった。ところが民族主義者たちは自分たちの隣りの民族を憎むことがドイツ人よりもはげしく、かれらを地上から消すために進んで協力するのであった。368P
ドイツ人はこのような者を棟や部屋の責任者として利用することがあり、そうした場合、異民族同士での殺し合いが横行することになったという。そうした事情が縷々述べられたあと、解放され、帰還するときの経験が興味深い。十日前に解放されたばかりというプラハを通った時は、彼が何者かを知るとプラハ市民は彼を下にも置かぬ歓迎ともてなしをしてくれ、バスの行き先を迂回してでも彼の目的地へと乗せていってくれるという体験をしたのに対し、破壊された故郷ブダペストでは冷たい対応をされている。
冷静にまとめられているけれど、その状況はすさまじいものがある。
メーセイ・ミクローシュ - 脱出 Mészöly Miklós(1921-2001)
これは難しい。落ち葉の収集焼却、庭の掘り返し、樹木の剪定その他多数の処理を、「住宅局」に指示され、それを知ったのが期限切れ間近だったため、家を逃げだして街を放浪するという話。ボロ屋になんとか潜り込んだ住人が立ち入ることもできない庭の管理を指示されるというのも不思議だし、それがなぜか期限切れギリギリで見つかるというのはまああるにしても、どこか不穏で、逃げだしてしまったけれども覚悟を決めて庭の清掃枝剪定をやりきったところで、「樹木保護局」の「労働者」が現われて、主人公夫婦を、我々の仕事を奪った、として責め立てるという展開がもうもののみごとに不条理きわまりない。その後みんなで火酒をやって終わり、というエンディングに至ってはもうなにがなにやら。
どうしてそうなるのかがまるで飲み込めない不気味さが全体を覆っているけれども、作中ではこれがきわめて日常的なことのように書かれており、どうにも不思議な作品。発表年は不明なものの、おそらくは戦後社会主義体制下で書かれたもので、全体主義社会特有の不条理感、迷宮感があり、その手の趣味の人にはとてもはまる作品だろうと思う。外国人が読むと何が何やらわからない印象だけれども、読む人が読めば、作中の描写や展開になにがしかの具体的な諷刺や示唆が読み取れたりするのだろうか。たぶんある種の全体主義社会ジョークというヤツだ。官僚社会、お役所仕事的社会の面倒さと、それを表だっては批判できない閉鎖感が、迷宮感や奇妙なユーモアとして現出してしまう感じの。
参考文献

- 作者: 南塚信吾
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2012/03/20
- メディア: 単行本
- クリック: 7回
- この商品を含むブログを見る
やや教科書的だけれども、序文で著者自身が、国民国家の相対化と農民など下からの目線を重視した、というように、ところどころでの短い記述になるほどと思う。農村と人民主義について触れたところなど、著者の他の著作『静かな革命』はこれを研究したものか、と興味を引かれる。コラム的な記事で、『ブダペストに春がきた』の主人公が研究してる「改革期のハンガリー語」というのが何なのか分ったのが面白かった。
序文では、近代日本のなかでハンガリーがいつから現われたのか、という点からたどり始めており、新書一冊よりもおそらく短い分量ではやはり著者にはまったく短すぎるのではなかったかと思われる。ハンガリー通史は新書クセジュの短いのと恒文社の大冊があるくらいなので、この著者にもっとまとまった通史を書かせるところはないのだろうか。

- 作者: 早稲田みか,チョマゲルゲイ
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2001/03
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 2回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
「ブダペストに春がきた」でも描かれる、ラーンツ・ヒードことセーチェーニ鎖橋の崩れ落ちた写真が見られる。ドイツ軍が撤退する時にすべての橋を爆破していったためとのこと。
面白いのは、巻末の著者プロフィールの生年がハンガリー動乱年基準で書かれていること。エステルハージの訳者らしく、文学関係も少々触れられており、一冊だけあるけれど、コンラード・ジェルジの他の作品の翻訳も欲しいと思った。

ハンガリー現代史 (1979年) (亜紀・現代史叢書〈10〉)
- 作者: 鹿島正裕
- 出版社/メーカー: 亜紀書房
- 発売日: 1979/11
- メディア: ?
- この商品を含むブログを見る
また、社会主義体制に対する期待を持って書かれていて、時代を感じる部分は多い。とはいっても、社会主義体制の裏面たる大規模な粛清についてもきちんと書かれており、特に1956のハンガリー動乱については、ハンガリーの「党史」がソ連幹部の介入を書いていないことを繰り返し指摘しながら叙述するなど、ずいぶんと冷静に見ていて、なかなか面白い。下記の大部の『ハンガリー史』では戦後が簡潔すぎるので、本書を参照せよ、とこの本の著者でもある訳者が書いているとおり、戦後についてこの時点ではかなりじっくり書いた本だろうとは思う。貴重。現代史としては山川の世界現代史の26巻も半分がハンガリー現代史になっているけれども未読なので後日。

- 作者: 羽場久美子
- 出版社/メーカー: 明石書店
- 発売日: 2002/04/25
- メディア: 単行本
- クリック: 12回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

中欧―ポーランド・チェコ・スロヴァキア・ハンガリー (世界の歴史と文化)
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1996/02
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
フランツ・リストはハンガリー生まれのリスト・フェレンツで、彼はしかしハンガリーで生まれたけれどもその生地は日常的にドイツ語が話される地域だったため、ハンガリー語ができないこともあり、あまりハンガリーでの活動が目立たなかった、というのが面白い。そして、父はエステルハージ家に仕える人物で、ドイツ語が使われるのもそのエステルハージ家の影響があったということらしく、こんなところにもエステルハージか、とハンガリーでのエステルハージの大きさには驚かされる。
また、ハンガリーは名前の順序が日本と同じく姓・名の順なのは有名だけれど、これがなぜなのかを解説しているのを初めて読んで非常に面白かった。これはつまり文法的な理由があって、「日本語やハンガリー語のように、ふつう修飾語が被修飾語に先行するような言語、あるいは「の」の付く所有表現において所有者が先に立つ言語においては、姓が先になるのが一般的なのである」と非常にクリアに説明されている。だから、住所も市が先で町名が後という風に大きい順から、日付も年月日と大きい順から書かれるらしい。また、このコラムでは伝統的な命名法では、女性は結婚すると自分の姓名を失い、誰であっても夫の姓名に女性形をつけたす形になる、という凄い代物だと言うことも驚いた。つまり、嫁になった段階で固有名を失う、というものらしく、だから既婚女性は旧姓名も常に併記するらしい。フェイェシの小説で、結婚した人でも誰でもフルネームで書かれているのは、それがあるからだったのかな。

- 作者: パムレーニエルヴィン,田代文雄,鹿島正裕
- 出版社/メーカー: 恒文社
- 発売日: 1980/05
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
著者名がハンガリー語なのだけれど、じつは原書は英語で編纂されたものに仏語版の増補部分を追加したものという。邦訳する通史に最適なものを選んだ結果、これが選ばれたとある。とはいえ、著者陣はハンガリー人らで、ハンガリー語の通史と同著者同文の部分があると訳者は指摘している。
ただ、本書自体の元版の年代のせいで、第二次大戦後の部分は政治的理由もあってか簡潔すぎると訳者に苦言を呈されている。とはいえそこで勧められている『ハンガリー現代史』もやはり古いので、体制転換後の成果を踏まえた戦後のハンガリー現代史は何かないかな。
私はもちろん通読したわけではなく、数ページ参照する感じで所々を拾い読みしているだけ。なので、全体の雰囲気については紹介できない。図書館で借りて読む本の気もしたけれど、こういう随時参照したいものはやはり手元にないと、と古書で買ってしまった。私には情報量が多すぎるとは思うけれど、まあ、いずれ通読することもあるかも知れない。
シリーズ過去記事
イヴォ・アンドリッチ - 現代東欧文学全集 12 ドリナの橋 - Close to the Wall
現代東欧文学全集1 ノンカの愛 他 ペトロフ〈ブルガリア〉 - Close to the Wall
現代東欧文学全集2 その男ゾルバ カザンザキス〈ギリシア〉 - Close to the Wall