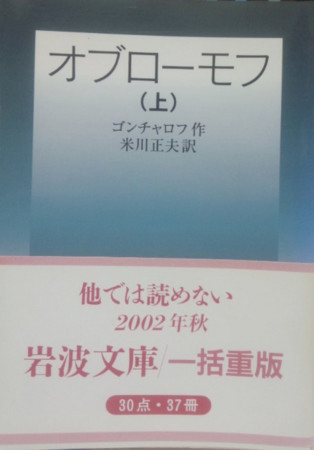- 作者: ゴンチャロフ,米川正夫
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1976/02/16
- メディア: 文庫
- 購入: 6人 クリック: 184回
- この商品を含むブログ (17件) を見る
というわけでようやっと読んでみたけれど、全三巻にわたる長篇で、波瀾万丈ということはなく、ある一地主オブローモフの特にどうということもない生涯を哀切に語っている。そして親友シュトルツ、下男ザハール、恋人オリガ、そして妻アガーフィヤらの周辺人物を丹念に描きつつ、「オブローモフ気質」という倦怠と退嬰の性質を浮かび上がらせる。
無用者、余計者の代名詞ともなったオブローモフという通り、序盤はベッドから出ることもなく、そして下男ザハールもそれにつられて無自覚の無能者として描写されている。ゴンチャロフ自身が有能な官吏がゆえか、オブローモフ気質を打ち出すのではなく、寝こけて怠惰なオブローモフは空想的退嬰に逃げ込んでいる人間という否定的人間像でもある。
中巻は第二篇、第三篇が収められており、第二篇はオリガとオブローモフの恋愛関係が始まりそして盛り上がるけれども、ここでオブローモフは関係の頂点で私はオリガの幸福のためならオリガを誰かに譲っても良いんだ、と誰か恋人候補がいるわけでもないのに勝手に言い出している。しかしこれはただの空想的自己陶酔でオリガを無視したロマンでしかない。
この空想的恋愛の高揚に対し第三篇では現実的側面が強調されてくる。いざオリガと結婚の約束をしたあと、ザハールからオリガと婚礼の話が飛び出るとオブローモフは恐慌に陥る。結婚資金やら準備が調っていないことに気づいて、見栄から噂の広まりを恐れて会わなくなる。むしろオリガの側は、オブローモフの困窮を聞き知って、自分の土地だか何かを提供すればとも思っているんだけど、オブローモフはただただ噂を恐れ、デートも気が気でなく、会うことすら避けてひたすらおどおどとしているばかりだ。これもまた俗世と見栄のエゴイズムでまったくオリガを見ていない。
オブローモフは自尊心の要求につり込まれて、オリガの心に犠牲を強要し、それに陶酔したくてたまらなかった。中巻293P
オリガもこう批判する。
「要りもしない、できもしない犠牲を申し出るのは、それは狡猾な人たちの手よ、要らない犠牲を捧げなくてもすみますからね。」中巻430P
結局オリガとの恋愛は破綻して、オリガの側が自分の恋愛は空想だったと省みるんだけど、もっと空想的なのはオブローモフ自身で、彼の行動がエゴイズムと自己憐憫への甘えでしかないことがグリグリと掘り下げられていくのが中巻で、なかなかすごい。
「オリガ、なんだってあなたはそう自分で自分をさいなむんです? あなたはぼくを愛しているんだから、とても別れてはいられないでしょう? あるがままのぼくを受け入れてください、ぼくのなかにあるいいところを愛してください。」中巻469P
オブローモフ気質というのがキーワードだけど、オブローモフのこの性格、いらつくと同時に、ある種の自分自身でもあるので、身につまされる面白さもある。さすがに酷すぎるだろと思いつつも、シュトルツに連れられないとどこにも行けない引きこもりぶりとか思い当たりすぎる。
下巻においてオリガとの恋愛が破綻したあとに見いだした、借り家の女主人は、家事を万端如才なく差配する有能な人物だけれど、自分の感情については無自覚な、無私の奉仕をこととする女性で、ある意味で旧時代的な主婦の理想像のような人物だ。このアガーフィヤの無私のオブローモフへの愛情は、オブローモフの自己憐憫の自意識の恋愛との対比ともなっており、進取の気性にとんだオリガとも対比的な人物だ。
じつはザハールの無能さとその妻となったアニーシャがきわめて有能に用事を全うするあたりにも、オブローモフとシュトルツの関係の似姿が埋め込まれていて、ラストにシュトルツが出会うのがザハールだということの意味がここにもある。
オブローモフ気質とは、怠惰と破滅の柩に入っているような生、という否定性のワードなので、オブローモフが終盤築いた何も変わることない「完全な幸福」はすぐに崩壊してしまう。もっと『怠ける権利』を主張したいところだ。働かないで生きていきたいよな。

- 作者: ポールラファルグ,Paul Lafargue,田淵晋也
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2008/08/01
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 60回
- この商品を含むブログ (24件) を見る
空想的ロマンにたゆたうオブローモフと対比されてる「ドイツっぽ」シュトルツの有能さ、勤勉さは近代資本主義社会のそれで、妻となる女性とのお互いに知性を高めあう関係と、オブローモフの日々変わる事なき生活およびその家主アガーフィヤが何の知識もないながら家事労働をきわめて有能に差配する様子の保守性とが、未来と過去として描かれるわけだ。
オブローモフ気質が否定性としてあるとしても、オブローモフの優しさ、人間的魅力については称揚されていて、特にアガーフィヤにとって太陽だったという件はなかなか泣かせるところがある。とはいえ、中巻あたりのエゴイストぶりが目立つので、その人間的魅力の真実性が感じられるかというと個人的にはやや疑わしい。未開人は心優しい、という類いのオリエンタリズム、というか、近代化しゆく時代において、滅び行く懐かしいロシアの典型としてオブローモフがあるようにも感じられる。過ぎゆく過去へのノスタルジーというか。柩に入っているようだ、とか、オリガにあなたは死んだ人だ、と言われる場面だとか、オブローモフはそういう象徴性を持っている。
それゆえにこそ、オブローモフ主義、というある種の典型を描き出したとして時代に名を残すことにもなったんだろう。ドブロリューボフの評論はそのうち読んでみたい。
しかし、アガーフィヤやアニーシャ、オリガなど、時代性はありつつも特に女性に対しては書き方がとても肯定的な感じがあるのはこの人の特質だろうか。オリガのオブローモフへの批判はいずれも的確で正しい。