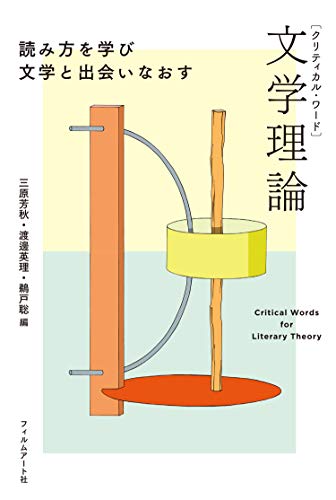二月くらいから読んでた本。
- ナイトランド・クォータリー vol.18 想像界の生物相
- ナイトランドクォータリーvol.19 架空幻想都市
- 高原英理『ゴシックハート』
- 高原英理『歌人紫宮透の短くはるかな生涯』
- 木村友祐『野良ビトたちの燃え上がる肖像』
- 木村友祐『幼な子の聖戦』
- 友田とん『『百年の孤独』を代わりに読む』
- 永田希『積読こそが完全な読書術である』
- 山本貴光『文学問題(F+f)+』
- 三原芳秋、渡邊英理、鵜戸聡編『クリティカル・ワード 文学理論』
- 小野俊太郎『フランケンシュタインの精神史』
- 荒川佳洋『「ジュニア」と「官能」の巨匠 富島健夫伝』
ナイトランド・クォータリー vol.18 想像界の生物相
岡和田さんが編集長となったと聞いて17号を読んで以来、一応知り合いがやってる雑誌ということでできるだけ追いついておこうと思っていたらこちらが読むよりどんどん新しいのが出てしまう。近場の本屋に置いてあることがまずないのもある。それはともかく、今号は、「怪獣絵師」開田裕治インタビューに始まり、ドイル「大空の恐怖」新訳やゴーレム譚、ヤズィーディーを扱った掌篇二つ、改変歴史ものの仁木稔の新作のほか、人魚を代償のテーマで再話したスラッター作が面白い。アンジェラ・スラッター「リトル・マーメイドたち」、人魚姫のアレンジだけど、魔女との取引というテーマで組み立てられた話が異形の存在へと帰結していくのがなかなかいい。スラッターは英国or世界幻想文学大賞受賞してる。ナイトランド誌のバックナンバーに受賞作がいくつか載っている模様。タラ・イザベラ・バートンの「レオポルトシュタット街のゴーレム」はユダヤ人街のナチスの難を逃れた家族のエピソードを軸にした一作で、これは西欧ウィーンのユダヤ人街が舞台だけど、『東欧怪談集』にも東欧ユダヤ、イディッシュのペレツ作のゴーレムもの短篇が載っている。仁木稔の「ガーヤト・アルハキーム」はイスラム教第六代イマームの息子イスマイールが主人公?の、「神や悪魔、精霊が実在する」イスラム世界を題材にした改変歴史もので、死せるものを復活させる器、不朽体という人工生命も出てくる。長篇の序章のようにも見える。友成純一のバリエッセイも面白いけど、目が悪くなることによる頭痛がだいたい同じ経験があるので、たいへんよく分かるところがあった。その他AIと幽霊の三宅陽一郎インタビューや怪異譚を補足するコラムやブックガイド、台湾映画その他。国書のマイリンクの集成が高騰してるのに気づいた……。ナイトランドクォータリーvol.19 架空幻想都市
異色の建築家、梵寿綱インタビューに始まり、創作では作中でも幻の都市を追い求める旅を描いたダンセイニ「カルカッソンヌ」が面白く、フォークナーの同名短篇が対比を刻むのが印象的。ダンセイニのはSFや現代文学にも似た感触がある。フォークナーの「カルカッソンヌ」は、ダンセイニが求道的な探索や死出の旅の寓話のようで古典的な荘厳さを持つのに対して、亡骸の語りというスタイルなどで喜劇化を図っているような感触がある。幻想性の頽落というか。じっさいにダンセイニのパロディなんだろうか。編集長岡和田さんによると、フォークナーが読んでいた痕跡は見つからないものの、両短篇を比較する英語論文を見つけたことが同時収録というアイデアの元になったという。解説にあるようにカルカッソンヌにcarcass=死体という単語が紛れているのが意味を持っている点は両作に通じるモチーフになっている。フランク・オーウェン「青碧の都」、これもまた死への道行きのようで幻想の都市が天国のごとき場所となっている。石上茉莉の「I am Lost」は異世界、鉱物、吸血鬼など多彩なモチーフを持ちながら、オーウェン作とも似た趣向で、ダンセイニ含めて異域への旅に死が重なる。マーク・サミュエルズ「暗夜庭苑」、月光熱という病気の治療のために訪れた廃墟のような場所が出てきていて、ヨーロッパとアメリカを未来と過去に象徴させつつそのすべてが滅んでいく頽廃の光景という雰囲気がある。続くウィリアム・ミークル「罅穴と夜想曲」は異星のパンクタウンという都市でディランやビートルズなどをレパートリーにするミュージシャンが記憶を拡張するなめくじみたいな生体的ガジェットを体に繋ぐという音楽SFで、身体拡張SFとしては図子慧作品とも通ずるしウォードの音楽ネタにも連繋する。幻の場所への通路が死を思わせるものがあれば、サミュエルズのほかリン・カーターやカイラ・リー・ウォードなど都市のほうが崩壊するものもあり、架空幻想都市というテーマが総じて死や崩壊の終焉の気配を共有しているのが面白い。朝松健の一休ものの幻のなかの京や、最後に友成純一のエッセイでジャカルタの鉄道怪談が幻想都市のオチを付ける感じも良い。私も文学フリマでちょくちょく買ってた垂野創一郎インタビューのほか、カルヴィーノやササルマンに触れたブックガイドに本誌テーマと同名のログアウト冒険文庫が顔を見せる。ダンセイニって河出文庫の作品集の一冊目出た時読んで、あんまりピンとこなくて続巻買わなかったんだよなー。ピンとこなくても買っておくべき本だった気はする。架空幻想都市で検索してエーコが『異世界の書 幻想領国地誌集成』っていうでかい本を出してるのを知った。虚構のなかの場所ではなく現実に存在すると信じられていた地球空洞説とかアトランティスとかを扱ったものらしい。『世界文学にみる架空地名大事典』ってのもあって、友人が持っていた。

- 作者:ウンベルト エーコ
- メディア: 単行本
高原英理『ゴシックハート』
「ゴシックな意識」を思想や理論や主義ではなく、黒や夜や荒廃、異端、異形など社会の序列から外れたものへの愛好を通した「クズな世界での抵抗のひとつ」と捉え、文学、絵画、写真、漫画、アニメなどさまざまな表現についての語りを通してその夜の世界へと案内する一冊。主義や理論ではない以上、評論といっても理論的な硬質さというより著者のスタイルから滲み出る「好悪の体系」を示すような論述は、やはり「語り」と呼ぶのが相応しいように思う。そしてゴシックにはスタイル、いわば「文体」が必要だというのが本書の主張でもある。「人外(にんがい)」の章では、江戸川乱歩、中井英夫から始まり、人間未満の存在『フランケンシュタイン』や高貴なポリドリの「吸血鬼」など「人間の外の世界に目を向けてしまう異端者」、人間以下・以上などのさまざまな「人外」の心を論じながら、そのゴシック性を取り出していく。「様式美」の章では、ゴシックの様式性について川端と三島について比較したところが面白い。三島は川端を名文家だけれども文体がないと語った。著者は、川端の描く美は外から現われるものを受け入れるもので「言語表現によって「世界」の意味を変えてやろうとは考えない」と言う。
三島由紀夫の告げた「文体」とは、要するに現世界に抵抗し、不可能であっても現世界の変容を意図せずにいられない者の言葉である。59P
世界に対峙し抵抗するための言語の武装が文体、スタイルにあるというわけだ。川端は耽美的であっても耽美主義ではない、と著者が言うのはこのこと。ゴシックなファッションもそうした抵抗としての装いといえる。「人外の心に敏感であり続ける者の表現が、その書き手の執着する様式に従って書かれる時、新たな耽美が生まれる」「ゴシックの精神としては、現世界への批判意識と自己の語法への厳格さが見られないものを称えることはできない」(60、61P)。怪奇趣味には雰囲気を醸成する技巧、スタイルが求められるのも同様だろう。そして著者はこう言う。
ゴシックのスタイルは本質的に過去の遺産の変奏と言ってよい。ただしその過去は実のところ一度もあったことのない架空の過去だ。ゴシックは十八世紀ヨーロッパの合理主義に反発して敢えて非合理的な中世に憧れる意識の書き残した物語を起源としており、そこに語られる中世の世界とは、古い建築の印象から形成された、歴史的事実によらない幻想だからである。9P
仮構されたフィクションに拠るスタイルという虚構性。
余談として、「なお「ゴスロリ」はマリスミゼルのManaが「エレガント・ゴシック・ロリータ」として提唱したコンセプトに端を発する」(17P)には驚いた。Wikipediaだけ見ても確かに界隈で大きな存在のようで、起源とまでは言えないようだけれど、自然発生的なものをコンセプトとしてまとめ、大きく広げる役割を果たしたらしい。
ゴシック、というと漠然としたイメージはあるけれど、という人にとって実例を元にしながらあるイメージを与えてくれるもので、扱っている題材については単行本の裏表紙が見やすい。最近立東舎から文庫化されたけど、単行本のミルキィ・イソベの装幀がやはり良い。文庫版は現物見たことないけど既に品切れの模様。

高原英理『歌人紫宮透の短くはるかな生涯』

- 作者:高原 英理
- 発売日: 2018/08/24
- メディア: 単行本(ソフトカバー)

本篇最初のページを見るとわかるけれどもテキストのように注釈欄がある版面になっていて、短歌の解説や関連語句の脚注が盛り込まれている。正確に言うと架空の歌人の架空の解説書を読んだ人間による叙述という三層構造のメタフィクション伝記小説になっている。
ゴシックな表現とそれが持つ意味合いなどは前項の『ゴシックハート』とも重なり合っていてその実作版という印象もあり、相互に読むとより面白い。和歌山生まれの紫宮透は、三重県出身で彼の三歳年上になる著者の分身にも見えるけれど、自伝的あるいは文化的空気の描出のためのギミックでもあるか。
「二○○○年以後ぼくたちはひどく貧しくなってしまって、そのせいか、給料が安くて人使いの酷い職場とか、いじめの経験とか、児童虐待とか育児放棄とか、人間関係の辛さとか、自分の無価値とか、そういうネガティブな話をどこかで織り交ぜないとリアリティに欠けるという思い込みの中で生きてますね。でもそれは普遍的なことなのかどうか、バブルの時代や好景気の頃の身勝手で面白おかしい、いい気な遊び心には、本当に真実がないのか、いや、真実なんてなくてもいいけどその面白い嘘には全く文学上の価値がないのか、紫宮透の、今では流行遅れと言われるような人工的な、自然体でない歌を読むと、思うことがあります」8P
2018年刊の本作の作意としてはこのセリフに示されているように、貧しくなった日本を踏まえ、軽佻浮薄の象徴としての80年代をゴシック歌人という遊戯的、人工的な芸術がありえた場所として捉え返す試みだろうと思われる。浮ついた生き方が可能だった時代。阿部和重『アメリカの夜』ではバイト中に本を読んでても良かったような頃を「小春日和の時代」と呼び、その終わりに言及するのが94年だった。
単に80年代を良かった頃として回顧するというよりゴシック短歌というこの世のものではないものを歌う歌人というアングルからやや皮肉に見る形を採る。短歌の解説だけではなく、伝説的に語られることの多い夭逝歌人についての事績を正確にたどることが必要だという理由で、歌の評釈として多くの論者の文章のほか、直接の知り合いの書いた紫宮についての文章などが多く引かれ、もちろんそれら架空の文章は歌の解釈とともに時代の空気を伝える。
そうしたエッセイ的な文章では80年代らしい、今から見れば痛い、としかいえないような文体のものも多くあり、いわば文体模写式に多彩なスタイルを本作に取り込んでいる。そこでは紫宮自身の文章にも固有名詞を散りばめた文化的な豊かな生活の誇示があり、確かに今から見れば「気恥ずかしい」。しかし80年代、経済が潤い、都市文化の絶頂とモダニズムの目覚めを迎え、裕福な層では労働より遊びが尊ばれ、「これほど日本人が「調子に乗っていた」時代は他にない」。良くなったことはもちろん数多いけれども、日本はこの頃より経済的に政治的にも端的に貧しくなった。
ゴシック歌人の生涯として面白く読めるのは確かだけれど、それ以上に80年代の青春というものをどう捉えるかというところで読み方が変わってくるように思う。ゴシックというオルタナティブな表現を通して現在のオルタナティブなありようもあったのではないかと問うているような印象だ。
紫宮透の趣味嗜好について最初は伯父から塚本邦雄を知ったことが大きかったけれど、それ以後は付き合っていた恋人たちに示唆された文学的先達がいなければ成り立たないというのが特徴で、いわば「男の趣味に影響された女」の逆を描いてるのが面白い。実際三島澁澤ジュネ足穂は女性読者が多い印象がある。
80年代の終わりに死んだ歌人をたどり、都市文化とともにその時代に生きた地方出身の人間の文化的背景を描き出しながら、親切に歌の解説を行なってくれる短歌入門にもなっている小説。
木村友祐『野良ビトたちの燃え上がる肖像』

- 作者:友祐, 木村
- 発売日: 2016/11/30
- メディア: 単行本
河川敷に小屋を建てて猫と暮らしている柳さんという男性を中心にして、アルミ缶集めで日銭を稼ぐホームレス生活の様子とともに、さまざまな事情でここにやってきた野宿者たち、寝たきりの父を介護する息子、DVから逃げてきた女性たち、寄付のしすぎで破産したライターといった人々が描き込まれる。現地取材に基づく野宿生活の描写は生々しく、しかしソーラーパネルでバッテリーに充電してテレビを見たりという、そこにも確かに生活があるということを浮かび上がらせる。河川敷はDVから逃げてきた女性たちやロヒンギャの青年といった難民的存在が集まってくる場所でもあり、そして時に猫が殺される場所でもある。
河川敷という川の増水で流されてしまう高さにおいてもまさに最底辺の場所とそこを見下ろすように建っているタワーマンションは富の偏在の象徴のようにそこにあり、「日本初のゲーテッドタウン」は物理的な壁によって貧富の境界線を区切る。そしてこの延長に死んでもいい存在を区切る境界線が生まれる。近隣住民は「野良ビト(ホームレス)に缶を与えないでください」という看板を出し、野良猫と野宿者を害獣のカテゴリに放り込み、ゲーテッドタウンに住む少年はボウガンで猫はおろか野宿者も狙い、「野良ビト」という野良猫と同じ、生きる資格のない存在だと強弁する。
木村作品に頻出する猫は、まさにこのような迫害しても良いものとして猫と人間の同一視を引き受け抵抗する足場となる。ここでは一部住民や少年によって、人間と猫の境界線が引き直されている。そして本作はまさにこの境界線をめぐる戦いを描こうとする。本作の近未来設定は読んでいてしばらく経たないとわからない。大企業優遇の税制と社会保障の縮小、そしてスポーツの祭典という道具立てはいま現在も懸案となっており、現在からまっすぐ続く近未来に本作の世界があり、現実とフィクションの境界線はどこにあるのかと問う。また作者として現われるライター木下は、現実の作者の分身のようでもありながら、家があるわれわれの側から野宿者側へと境界線を越えていく可能性の分岐でもある。メタフィクション的な部分はそうした境界線を越えうる存在として木下があることの証しでもあるだろう。
終盤柳さんが猫と「同じ獣としての吠え声を発」するのは、人間が猫の側に投げ出される境界線の引き直しを引き受けることでの抵抗だ。貧富の差、人間と猫、住民と野宿者、作者と登場人物。境界線をめぐる闘争はだから、川というまさに境界線そのものを舞台にして描かれることになる。どうでも良いことかも知れないけど、野良猫にも野良ビトにも、「野」と「良い」という文字が使われている。
ただ、面白いけれどもやはり直截すぎるなと思う点もいくつかあって、未来設定とか、『〈野宿者襲撃〉論』を反映したゲーテッドタウンの少年とか、気の狂った人間が高笑いする場面とか、作り付けが甘いと感じるところも結構ある。しかし、一見安直にも見える政策などは、つねにこの現在の延長にあり得る未来のデフォルメとなっており、どこかの時点でその延長線を断ち切らねばならないという危惧と、そして本当に区切ることができるのか、という問いになっている。そんなわかりやすいアレな政策ないだろう、と思うとしかし現実がその先を行くのが今だ。
作者がモデルとなった人とのことを書いたエッセイ。
ヘテロトピア通信 第16回 | SUNNY BOY BOOKS
木村友祐『幼な子の聖戦』
東北の小村で行なわれる村長選挙で保守党県議の脅迫で応援していた幼馴染みを裏切って妨害工作を行なうようになる男を描いた芥川賞候補の表題作と、ビルのガラス拭き会社に勤める新人の視点から職人の仕事のありようとその尊厳を無視して憚らない現実を描き出す二つの中篇。『パラドックス・メン』「幼な子の聖戦」「犬のかたちをしているもの」「会いに行って――静流藤娘紀行」「かか」「改良」「正四面体の華」『黄泉幻記』『夢の始末書』 - Close To The Wall
「幼な子の聖戦」は雑誌で読んだ時の感想は既に書いたけど、選挙electionと勃起erectionが日本語だと同音になる、という「勃起力」をめぐる記述や、主人公が人妻クラブというところで女性と関係したことが脅迫のネタになるなど、男性性をめぐる話でもある。家長を掴めば投票は家族ごと取れるという選挙戦略も家父長制による「伝統的」なそれだし、そもそも元村長の辞職がそうした性的スキャンダルによるものだった。そこで女性層を引きつけた仁吾と、老人たちを「資源」とする保守派との抗争の構図。それが単純だともいえるけれど現実が違うとはとても。
そうした新旧対立のなかに主人公が自身の虚無とともに考えているのが宗教性についてのモチーフで、過去新興宗教に勧誘された時の経験やこの地にマリアがやってきたという胡散臭いアベマリア伝説が絡んでそして自分の行動を「聖戦」とみなしながら信仰されるべき伝説を創造しようとしている。「幼な子」の無垢さとこちらを見る子供と猫の無垢な視線との重ね合わせもありながら、自分のなかでまだここら辺の題材の関係がわかってないところがある。大きな政治そのものを扱うにあたってここまで宗教性が出てくることの意味はいろいろあるはずだけども。新郷村がモデルというのもあるけど。
「天空の絵描きたち」、古市憲寿の芥川賞候補作の元ネタとして話題になったけどそっちは読んでない。デザイン会社からゴンドラやロープで高層ビルの窓ガラスを拭く清掃会社社員へと転じた女性がその仕事に慣れていくのとともにベテランの仕事の鮮やかさに魅せられる。タイトルの比喩は窓を拭く動作がペンキ塗りに似ている、という意味かと思ったらかなり違っていて、ビルのなかから外を見る時に額縁になる窓を掃除することで、外の景色という絵を窓に映し出す、という意味合いで使われている。内と外との境界線をクリアにするわけで、主人公もまた窓の内から外へと転じた。ロープに命を託して行なわれる現場仕事の様子を丁寧に描きながら、会社の方針で仕事が値下げされ、窓拭きの仕事へのやりがいすら奪われ、挙句には備品に金を掛けない状況が死亡事故を招くという、さまざまな意味での貧しさとそれに抵抗する労働者たちの様子が描かれている。
「けど、たかがガラスでも、自己満足も許されない仕事なんか、やる意味がないっておれは思うんだ。人生のほとんどの時間は、仕事なわけでしょ?」(中略)「結局そうやって、おれらはどんどん、働く喜びさえ取り上げられているんだ」170-171P
構図はシンプルだけど地味で危険な仕事を爽やかに描く。装幀なかなかいいな、誰だろうと思ったら仁木順平だった。松籟社の東欧の想像力シリーズのいまの担当をしている。
友田とん『『百年の孤独』を代わりに読む』

『百年の孤独』を代わりに読む|代わりに読む人
「代わりに読む」というコンセプトを手がかりにガルシア=マルケスの名作を一章ずつ、著者自身の知る作品に引きつけながらできるだけ脱線しながら読んでいくなかで、代わりに読む過程が著者自身の『百年の孤独』を「代わりに書く」ことに至る奇妙な読書録。自費出版というか、通販以外では限られた書店でのみ入手できる。三年前に出た年にはすでに買っていたんだけれど今更読んだ。
著者は一見意味不明で冗談のような「代わりに読む」という言葉を差し出しながら、ひとまず「あなたの代わり」に私が読む、として読書を開始する。本文自体は原作一章ずつの物語内容を説明しながら、誰々は私が知ってる他の作品の誰々に似ている、と別の作品などに強引に引きつけたりしながら脱線混じりに進んでいく。一見関係のないことを書くのは『百年の孤独』もまたさまざまな無関係に思われた挿話が積み重なっていくからだといい、田中美佐子の出るドラマに言及したりドリフのコントに似ていると言ったり「バックトゥザフューチャー」や伊丹十三の「タンポポ」を引き合いに出したり、脱線は尽きない。
脱線や冗談が世界を広げていることだとか実在しない湘南新宿ラインだとかの脱線、転線論も面白いけれども、見事だと唸ったのは17章、『百年の孤独』で部屋の片付けが出てくると話がこんまりこと近藤麻理恵の片付け本の内容と次第にごっちゃになり、その入れ替わりを回収するように最後に『百年の孤独』の双子の墓穴の取り違えという場面で終わるところだ。これは上手い。そして終盤、メルキアデスの羊皮紙解読が話題になっていくわけだけれど、ひたすら羊皮紙を読んでいくアウレリャノはもちろん本書の著者とも重なっていくし、『百年の孤独』は読んだことがあるので、これらが絡んでいく「ラスト」の大枠は見えてくるんだけど、それでも最終盤は圧倒された。
最後をどうするかという悩みを知人に相談したら「ラストどうしようかって、それ変じゃないですか?」と言われたと書かれているとおり、読んでるだけのエッセイがメタフィクションの構造を持つ原作と響き合って、読むことをめぐって書かれた『百年の孤独』のパロディという「フィクション」にも似た本書を生み出してしまう。『百年の孤独』という強靱な土台があるからこそ、そしてその羊皮紙をめぐる構造があるからこそ、このような芸当の土台になり得るわけで、合わせ鏡のなかに消えていくマコンドという「鏡の(すなわち蜃気楼の)町」の反射が本書を生み出すのが、読むということでもあるような感覚。
そしてこれは読書エッセイのかたちをとった後藤明生の『壁の中』ではないか、とも。『壁の中』はドストエフスキー『地下室の手記』のパロディから発して無限に脱線を続けていくことで書かれた作品だったけれども、つまり本書はガルシア=マルケスを後藤明生で読む、という試みではないか。『百年の孤独』は周知の通り「孤独」がテーマになっていて、まさにそういうラストなんだけれども、著者はそこに一族の歴史を「代わりに読む人」を見出している。自分以外のもう一人、つまり「読む」ということ、「代わりに読む」ということは孤独な一人を二人にする行為として捉え直される。代行とは必ず二人以上を必要とする。後藤明生の読むことと書くことの関係が引用されているけれども、読むことが書くことに繋がる関係は、一つのものが無限に複数化していくメカニズムでもある。そもそも、本書表題の「孤独」を「代わりに読む」という時点で言葉での対比が仕組まれている、かも。
なんにせよ、『百年の孤独』を「代わりに読む」ことが著者によるもう一つの『百年の孤独』を「代わりに書く」ことになっていく過程にはおお、と思わせるものがあって、カラーページの挿入もここぞという感じでアウレリャノとの重ね合わせも決まっていた。
恵贈いただいた新著については先に記事にしてある。
秋から年末にかけて読んだ本 - Close To The Wall
永田希『積読こそが完全な読書術である』

- 作者:永田 希
- 発売日: 2020/04/17
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
本を読むことには、前書きや参考文献等をチェックする点検読書、テーマで横断するシントピカル読書、精読する分析読書などさまざまなものがあり、読んでない本についてもそうしてその本の文脈や評価を頭に入れ、自分なりに本のネットワークを構築することを著者は「ビオトープ的積読環境」と呼ぶ。著者が幾度か言及する、汚れた本の山のなかで尿を紙パックに溜め込んで家族に暴力を振るいアル中になっていた人物をセルフネグレクトと呼んでおり、ビオトープの構築は「自己の輪郭」を適切に管理する、という生き方の問題に繋がっていく。本という形で自己を適切にメンテナンスすることが。
本書の問題意識は、消化しきれない情報が流れていく現代において、そうした自己の足場をいかに作るかということにあり、積読という外部化された自分の興味関心のありようを常にチェックしていくということが目指されている、と思われる。本棚のメンテナンスを重要視するところは以前書評を書いた『中年の本棚』などで荻原魚雷も説くところで、点検読書などでのチェックや関連づけはしばしば言われてることでそこまで目新しいことではないけど、古今の読書論を参照しながら表題の逆説を説いていくところはなかなか面白い。
また、リスクや保険、金融について中世史を参照したり、使われることを志向しつつ貯め込まれることでも意味を持つ貨幣の書物との共通性を指摘したり、ブラックボックスとして目の前にあるコンピュータを関連づける発想については、私は未読だけど、ちょうど完結した集英社新書サイトでの連載が扱っている。そのうち集英社新書から刊行予定とのこと。
カネは書物、書物はカネ 情報流通の2つの顔 – 集英社新書プラス
人間に完全な読書はできずとも、「どんなに不完全でもあっても、何かを書き、それを積むことで、いつか誰かに読まれるかもしれないということ、誰かがいつかそれを読めるかもしれないということは、書物を生み出し、それを継承し続ける限り、何かを読める人の希望であり続けるからです」(230P)という本書の一節と、友田とん『『百年の孤独』を代わりに読む』での、「小説を人の代わりに読むことはできないというのは希望である」(201P)、というのはほとんど同じことを言っているな、と思った。積むのに向いたブックデザインが秀逸で、またカバー裏では積み本が崩れているのが面白い。
山本貴光『文学問題(F+f)+』

- 作者:貴光, 山本
- 発売日: 2017/11/24
- メディア: 単行本
退屈で難解と評される『文学論』を、その前の言葉という側面から捉えた『英文学形式論』からたどって、漱石の文学論を形式と内容両面から把握する。漱石はFがあってfのない文章を例えば科学についての文章だとし、情緒に働きかけるものを文学として捉える。
漱石は、文学とは認識のみならずそれに伴う情緒(F+f)を表現したものであり、書かれていることが事実か虚構かを問わず、読者を幻惑してなんらかの情緒をもたらすものだと考えた。433P。
漱石の理論で現代文学を読んでみる、という章はちょっと物足りない感じもするけれども、科学の文章を文学の文章と対置していた本論の延長上で、数学的記述を小説に盛り込む円城塔の小説を扱うところはこれがやりたかったのでは、と思わせる。
意識の流れ等の元になったジェイムズの心理学に影響を受けた漱石は、何に焦点が当たるかという競争が行なわれる人の意識は不断の修羅場だとも述べており、これは集合的Fとして人間社会に対しても拡大して用いている。文学と読者のみならず社会との相互関係も視野に入れている。文学を読む批評理論としての文学理論ではなく、文学とはなにかという原理論の探求として人間の感情を重要な要素とした漱石の文学論をベースにすることで、批評理論のみならず心理学や脳科学と文学の結節点となる現代の学問への広がりをもフォローアップしていくことになる。圧巻なのは『文学論』のダイジェスト版のような要約と解説を行ないつつ、現代の多様な関連学問への膨大なリファレンスや、発表以来110年にわたる『文学論』評価を適宜抜粋しながらまとめた40ページ近い資料篇など、『文学論』を現代に読み、使うための参照データの充実具合だ。
脚注に提示された欧文を含む参照文献の物量やジャンルの広さは文学論を起点にした一大ブックガイドの趣を呈しており、根こそぎという感じがある。漱石の理論自体にはわかったようなわからないような索漠とした感じが残るけれど、広がりがありすぎるのかも知れない。
三原芳秋、渡邊英理、鵜戸聡編『クリティカル・ワード 文学理論』
2020年刊行とかなり新しい文学理論概説書で、前半を編者らによる基礎講義編、後半を院生らによるトピックス編という二部構成で、特に後半はポストヒューマニズムや環境と文学など類書にあまりない章構成でかなり新鮮な目次になっている。第一部は「テクスト」「読む」「言葉」「欲望」「世界」というテーマを立てた基礎講義で、文学理論を横断的に参照しつつそれぞれ具体的な作品を扱って読解の実例を示したりしながら、末尾にそれぞれ用語解説とブックガイドを付す形式を採り、いかにも入門講義の体裁となっている。デリダ、バルト、蓮實重彦を題材にした郷原佳以「テクスト」、芭蕉の俳句の読みから始まり、対位法的読解、妄想的読解、徴候的読解などを論じる三原芳秋「読む」、ドゥルーズ・ガタリのマイナー文学やサイードを援用して崎山多美や李良枝を扱う渡邊英理「言葉」、『フランケンシュタイン』を論じつつフェミニズム、ジェンダー、クィアの議論をたどる新田啓子「欲望」、インドネシア文学を題材に国民国家と近代文学の関係や出版流通の問題を論じる鵜戸聡「世界」と、さまざまな切り口から議論が行なわれる。
トピックス編は基礎的な用語・概念から未邦訳文献をザクザク紹介しながら最新の話題までを二段組で情報量を詰め込む。ネグリチュードからポストコロニアリズム、世界文学論までを含む橋本智弘の六章、ポストヒューマンや動物研究、人類学の存在論的展開から思弁的唯物論までを扱う井沼香保里の七章。エコクリティシズムやネイチャーライティング、震災文学までを含む磯部理美の八章、精神分析の森田和磨の九章、ジェンダーセクシュアリティの諸岡友真の十章と、講義編と重複する点も多いのは、女性とポストコロニアリズムなど議論が各章で相互に関連しており截然と区分けできないからだ。
そうした構成ゆえでもあろうか、ジュネットが索引になく用語解説で触れられる程度で物語論や言語学、受容理論などはフォローされておらず、文学理論のカタログとしては弱い部分もある。おそらくは既存の概説書を踏まえつつ今の文学理論のありようを提示するのが本書の趣旨だろう。「欲望」の章で近年のクィア議論を紹介するなかで、エーデルマンが「社会の維持を目指さない(反社会的転回)という純然たる否定性こそ、クィア理論が目指すべき方向(クィアな否定性)である」と言っているというのはなかなか面白い。メイヤスーの思弁的唯物論は解説を読んでもよくわからなかった。
最後に、松籟社で世界文学アンソロジーを編んでいる鵜戸聡によるマイナーな地域のものを重点的に紹介した「世界文学(裏)道案内」や文学理論概説書のブックガイドがついている。これもなかなか面白い。
20世紀の文学理論概説としては手元に96年刊の『ワードマップ 現代文学理論』があり、学生時代に読んだ覚えがあるけれど、そこでは記号論や構造主義、物語論、テクスト論が扱われており、文学理論が構造主義の展開と密接な関係を持っている歴史は、本書で最初にざっと出てくる程度だ。ワードマップとクリティカルワードの目次を帯裏で見比べるとかなり違うのがわかる。90年代の文学理論概説書はポストコロニアル批評って最後の方に付け足されてることが多いしワードマップにはサイードが索引にないんだけど、クリティカルワードの方では頻出人名の一つ。ここ数十年でポストコロニアルとジェンダーの重要度がかなり大きくなったのがわかる。
六章担当の橋本智弘さんは『ノーベル文学賞にもっとも近い作家たち』で一緒になったことがある。氏はこちらでラシュディについて書いている。

- 発売日: 2015/07/01
- メディア: Kindle版
小野俊太郎『フランケンシュタインの精神史』

フランケンシュタインの精神史: シェリーから『屍者の帝国』へ (フィギュール彩)
- 作者:小野 俊太郎
- 発売日: 2015/08/19
- メディア: 単行本
第二部は未読の作品も多くやや議論が頭に入ってこないところもあったけれど、第一部は、たとえば当時のイギリスが複数の国のつぎはぎの領土として国民国家を形成していたことを怪物のつぎはぎと重ねるような、こじつけに見えるけどなかなか面白いところがたくさんあって、いろんな知識を背景にした切り口の多さは読み込みのとっかかりにもなるし雑学としても面白くて『フランケンシュタイン』を多様な側面で読んでみる実例集になっている。科学の知識がイスラムから再輸入された話は有名だけど、その書の『キタブ・アルキミア』という題名がアルケミーやケミストリーの語源だったり、アルコールなどのアルという接頭辞がアラビア語の定冠詞に由来しているというのも面白い。出身地ジュネーヴに関してルソーと関連させてみたり、怪物がフランス語を学んだことや怪物は果たして男性なのかと改めて問うてみたり、作品を改めて見直す契機になる。
第二部は戦後日本におけるフランケンシュタインのテーマを、人造人間やロボットと関連させて手塚治虫や石ノ森章太郎、銀河鉄道999、キカイダー、セイバーマリオネットなどの作品や、小松左京、光瀬龍、田中光二、荒巻義雄、山田正紀などの戦後SFの作品に見出していく。そして『屍者の帝国』が既存作の継ぎ接ぎとして書かれていることに至る。本書を著者は
戦後すぐの民主主義国家の住人への改造や変身を重視した第一段階から、対抗文化のなかで人間回復をめぐる議論をしていた第二段階を過ぎ、複製や複合が当然視されるなかでの「生」をしめす第三段階となった。233-4P
とまとめている。あかほりさとるの『セイバーマリオット』や日日日『ビスケット・フランケンシュタイン』というライトノベルにも言及するけれど概ね戦後の代表的なSF作品やSF作家をたどる形で、マイナーな作を網羅する方向ではない。個人的には前半が面白かった。
荒川佳洋『「ジュニア」と「官能」の巨匠 富島健夫伝』

- 作者:佳洋, 荒川
- 発売日: 2017/01/27
- メディア: 単行本
私は一作も読んだことがないけれど、これを読んだのは富島が後藤明生と同じく植民地朝鮮生まれの引揚げ作家だったからだ。そういう興味だったんだけれど、引揚げ作家という点以外でもジュニア小説、官能小説という文学のアウトサイドで活動した作家の評伝として面白く読んだ。引揚げ作家としても自伝的作品などいくつかはそのうち読みたいと思ったし、作品にも多くその影響が認められることもうかがえて興味深い。価値観の転変という昭和一ケタ生まれの問題は後藤も述べていたし、すべてを失って引揚げてきたゆえの国や集団への不信なんかも通じるものがある。
そういう部分以外でも、富島はジュニア小説においてもつねに文学をやるつもりで書いて、それが大ヒットしたわけだけど、その後『おさな妻』での性描写がメディアで議論となり、保守派からの批判に遭い、当時いくつもあったジュニア小説誌が70年代初め頃、次々と休刊していってしまう。多くが教育系出版社だったジュニア小説誌にとって保守的な論調には逆らえなかったとあり、とするとジュニア小説の潮流というのは人気の下降ではなく、保守的なバッシングによって消えた、というのはいかに当時の性描写への批判が強かったか、ということだろう。
少女小説の流れを汲むジュニア小説において、その流れに対して富島は自分は少女小説を書くのではなく、十代を主人公にした文学を書くつもりで書くという方針で少女小説にある多くの制約を人気作家の後押しで一つ一つ破っていった、という。それが潰されたあと、富島は官能への撤退を行なう。70年代から富島は官能小説を多く書くようになるけれど、あるエッセイで「嘘と偽善と権謀術数にこりかたまった現代への不信感が、彼をして官能の世界に侵入させた。女体への自己のあこがれ、また女体から受ける自己の感覚だけは現実性ある真実だと、彼は考えた」(243P)と書く。官能小説の主人公の背景でもあり富島自身のそれでもある。毛沢東を敬愛し文化大革命を支持したアジテーションを作中に込めていた作家でもあった彼の政治不信がエゴイズムと官能への立て籠もりへと至ったわけだ。
著者は70年中頃、富島四〇歳頃までの作品を評価して、それ以後の作品は一部を除いてあまり評価していない。それは当然本書の構成にも現われており、官能小説を書くようになる頃は既に本書終盤だ。本人の資質としては性を書きたがったけれど、青少年を対象にしているというのがそれを抑える良い制約になったという指摘が示唆的だ。
しかし、富島がジュニア小説誌で女性読者から処女性について問われた時に「どんな名器でも処女には及びません」と即物的な応答をしていることに著者が思いっきり引いてるところは笑ってしまった。メンタルの話を聞いたら性交時の快楽の話が返ってきて、「処女」の価値は男が決める、という言いぐさもすごい。しかしその大事にすべきものを食い荒らす官能小説での男性のプレイボーイぶりとあわせるとこれは単なる「処女嗜好論」ではないか、と著者が批判しながらも「男性"性"」の肯定抜きには富島文学が成り立たないものでもあると指摘するところはフェアな態度だろう。
富島健夫が文学を志向しつつその傍流で生きるしかなかったのは、書く力はあるのに他人に頭を下げて雑誌に中短篇を発表することを良しとせず、芥川賞レースに参加しなかったことで時評などの「文壇」から疎外されてしまったこと、という著者の指摘がある。文芸誌に書くことをせず、長篇書き下ろしで勝負したわけだけれど、それらはほとんど話題にならず、若者雑誌に書いた青春小説が評判を取ることで十代向けにシフトしていくことになる。文学を志向するなら、やはり中短篇を雑誌に発表して行くべきだったのではないか、と著者は言う。知り合いに多くの作品を見せているし、それができる実力はあったはずだ、と。
私の関心のきっかけでもある後藤明生が一度出てくるところがあって、学生時代に河出書房に来たら富島がゲラを校正しているのを見て羨望を覚えたというものだけれど、出典がないのでこれは著者自身が直接聞いた話だろうか。後藤が富島に言及したことがあるかどうか、あまり記憶にない。なお後藤と富島は生没年が一年違いでほとんど同じ年を生きている。後藤は32年から99年、富島は31年から98年。九州に引揚げ、早稲田に入ったのも同じで、また「文藝」復刊まで開かれた「文芸の会」には後藤も出ていたので、おそらく両者には面識があったはずだと思う。
やや年上の同じ朝鮮引揚げ作家の小林勝が、學燈社の雑誌「若人」でやっていた連載の後枠に富島を推挙したことがあり、それが富島の初めての商業誌からの依頼だったというのが面白い。この交番焼き討ちで捕まった作家が青春小説作家誕生のきっかけにもなってるというのは数奇だ。富島は小林と縁があったわけだけど、後藤明生も小林の作を書評で酷評した因縁があったりする。さらに引揚げて後、富島が九州福岡の豊津中学に通っていたと言うから驚いた。これは鶴田知也や葉山嘉樹、堺利彦の母校だ。鶴田知也は私の最初の商業原稿で扱った作家でもあり、そう繋がるのか!と非常に面白かった。後藤も富島も植民地生まれだけれど、来る前は九州に本家があるからここら辺はなるほど近い。富島は朝鮮では京城の龍山国民学校に通っていたけれど、ここはその前身を龍山公立尋常小学校といい、中島敦が卒業している。また富島がその後通った龍山中学は中島敦の父が教えていたことがあり、そこには同じく引揚げ作家の日野啓三が二年上にいたという。
舟木一夫「高校三年生」が富島原作の映画の主題歌だったらしいのは初めて知った。ただ、これは歌がヒットしたことで作られた映画だというから、曲が先にあって映画の題材として富島の作品が使われた、という経緯に見える。『明日への握手』という原作小説の名がしばしば間違われるのはそういうことだろう。
というわけで、積んでる本のうちツイッターで相互フォロワーの人がかかわった本、という縛りで読んでみた。相互と言っても特にやりとりがあったわけでもない人もいるけれど、さすがに関心領域に重なるところが多かった。